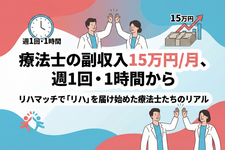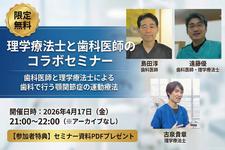令和7年春の叙勲が2025年4月22日(火)の閣議で決定され、4月29日付で正式に発令されました。今回の叙勲では、厚生労働省関連の受章者が412名にのぼり、その中には作業療法士として制度の発展に尽力してきた長尾哲男氏(76歳)の名前も含まれています。
長尾氏は、日本作業療法士協会の元副会長として、長年にわたり作業療法士の職能確立や制度化を牽引してきました。また、長崎大学医学部の教授として教育・研究の両面においても活躍し、地域医療や障害福祉の現場で実践力のある専門職を数多く育成してきました。
このたび授与された瑞宝小綬章(ずいほうしょうじゅしょう)は、国家または公共に対して長年にわたる顕著な功績を挙げた人物に授けられる名誉ある勲章です。長尾氏は、「保健衛生功労」および「教育研究功労」の両分野において高く評価され、今回の受章に至りました。
制度の草創期から尽力
作業療法士制度が社会的に認知される以前から、長尾氏はその重要性と役割を各方面に訴え、制度の基盤づくりに大きく寄与してきました。1986年から1998年までの期間にわたり、日本作業療法士協会の副会長および理事を歴任し、職能団体の中核として制度整備に関与した実績を持ちます。
大学では、学部教育だけでなく大学院での研究指導にも尽力し、認知症リハビリテーションや精神科作業療法の分野でも実績を重ねてきました。とくに高齢者の精神・心理的機能に関する研究は、臨床への応用と学術的意義の両面で評価されています。
地域と教育の“架け橋”として
長尾氏は、退官後も地域保健や福祉の分野において活動を続けています。大学と地域、教育と臨床、制度と実践といった領域を横断し、“架け橋”となるような存在として貢献を重ねてきたことも、今回の叙勲にあたって重要な評価要素となったとみられます。
療法士界にとっての象徴的受章
本受章は、長尾氏個人の栄誉にとどまらず、作業療法士という専門職全体の社会的評価向上にもつながるものです。医師や看護師に比べ、叙勲を受ける機会が少ないとされてきた作業療法士にとって、今回の受章は公共福祉への貢献が広く認知され始めた証とも言えます。
療法士の専門性と社会的意義を再認識するうえでも、長尾氏の受章は今後の職能発展に大きなインパクトを与えることでしょう。