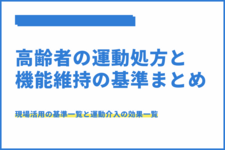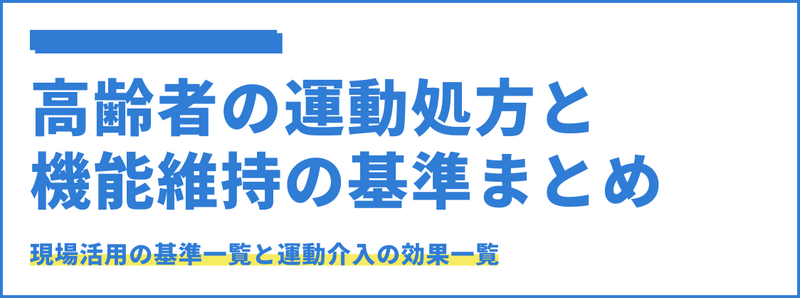
目次
- はじめに
- 1. 高齢者の定義と機能評価基準
- 2. 運動処方の科学的根拠
- 3. 生活機能維持の最低基準
- 4. 年齢層別運動処方の実践
- 5. フレイル・サルコペニアの予防と管理
- 6. 実践上の注意点と限界
- 7. まとめ
- 参考文献
はじめに
日本は世界でも類を見ない超高齢社会を迎えています。理学療法士にとって、「高齢者がどの程度の運動をどのくらいの頻度で行えば生活機能を維持・改善できるのか」という問いは、臨床で日常的に直面するテーマです。
研究やガイドラインからは、歩行速度・握力・SPPB(Short Physical Performance Battery) といったシンプルな指標が、生活自立を左右することが明らかになっています。また、適切な運動処方は身体機能だけでなく、認知機能や生活の質(QOL)の改善にも直結します。
本記事では、日本および国際的な基準を整理し、最新のメタ解析の知見を踏まえて、臨床現場で「すぐ使える」評価基準と運動処方の目安をまとめます。
1. 高齢者の定義と機能評価基準
1.1 高齢者の定義
- 日本:65歳以上を「高齢者」、75歳以上を「後期高齢者」と定義(厚労省)。
- 国際:WHOや米国CDCも65歳以上をolder adultsと定義。
▶︎臨床Tip: 「75歳以上は生活機能低下リスクが急増する年齢」と説明すると理解されやすい。
1.2 年齢層別の機能低下リスク
- 65–74歳:約3.5%がADL支援を必要とする
- 75–84歳:約7%
- 85歳以上:約21%
▶︎臨床Tip: 「70代までは元気でも、80代から急激にリスクが高まる」と伝えると介入の動機づけになる。
1.3 機能評価のカットオフ値
- 歩行速度:1.0 m/s以上が望ましく、1.0 m/s未満は機能低下、0.8 m/s未満は予後不良ライン。
- 握力:男性28kg未満、女性18kg未満でフレイル・サルコペニアリスク。
- SPPB:9点未満で要介護リスク。
診断精度:歩行速度や握力はいずれもフレイルの判別に有効で、歩行速度は特に高い精度を持つことが多く報告されています。
▶︎臨床Tip: 「歩行速度1.0 m/s以上を維持」が生活自立ライン。患者説明やゴール設定に有効。