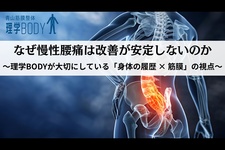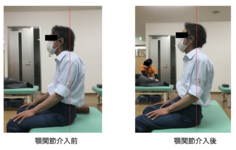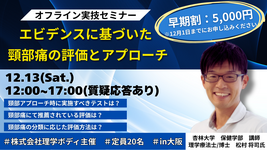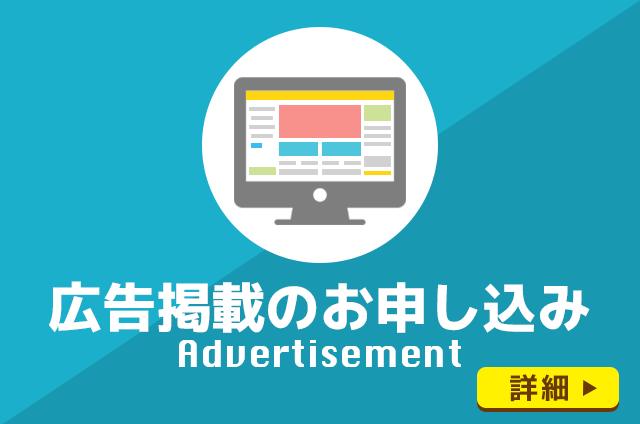Voice ─ 現場からの提言
徳島・鳴門で実証された
「年間30万円」の衝撃と、
40年変わらぬ現場への問い
前編 ─ 川下から川上へ。一人の理学療法士が辿った38年の軌跡
12月。徳島の空は低く曇り、時折、唸るような強風が吹き付けていた。徳島文理大学へと向かう道中、私はある種の「違和感」について考えていた。
「2025年問題」や「地域包括ケアシステム」──国が旗を振り、あれほど叫ばれてきた言葉を、当の2025年を迎えた今、現場であまり耳にしなくなっている。制度という「器」は完成した。システムは構築されたことになっている。だが、熱狂は去り、ただ冷たい仕組みだけが残されたようにも見える。
そんな問いを抱えながら、私は鶯(うぐいす)春夫氏の待つ教授室のドアを叩いた。
部屋に入ると、鶯氏はデスクいっぱいに資料を広げて待っていた。過去の研究データ、行政との実証実験のグラフ、住民の変化を追った記録……。取材のために時間をかけ、丁寧にプリントアウトされた膨大な紙束に、鶯氏の取材に対する誠実さと、研究者としての準備の深さが滲んでいた。
"『器』はできました。
── 鶯 春夫 氏
しかし、中身はどうでしょうか
鶯氏は穏やかな口調で切り出した。決して声を張り上げるわけではない。ただ、用意してくれたデータシートの一枚を、指先で静かに示した。そこには、感情論ではなく、長年の検証によって導き出された「事実」だけが記されていた。
『要介護認定率の抑制、医療費・介護給付費の削減効果』
かつて病院という密室で、終わりのない徒労感に苛まれていた青年は、いかにして行政を動かす「論理」を手に入れたのか。これは、一人の理学療法士が「川下」から「川上」へと遡った、38年間の記録である。
単位と売上の日々に感じた「虚無」
時計の針を1986年に戻す。新卒で入職したのは、新設されたばかりの整形外科病院だった。最新の設備、治っていく患者。理想的な環境に見えたが、現場の空気は乾いていた。求められたのは「治療」ではない。「点数」だ。いかに単位を取るか。いかに売り上げを稼ぐか。
数字に追われる日々の中で、鶯氏は自身の腕が錆びついていくような危機感を覚えた。「このままでは、自分がダメになる」。彼は恩師の元へ走り、わずか1年でその場を去った。
翌87年。彼はリハビリテーションに理解のある院長を求め、老人病院(橋本病院)へとたどり着く。そこは、前の職場とは対照的だった。病棟には、独特の匂いが漂っていた。消毒液と、湿り気を帯びた澱んだ空気が混じり合った、病院特有の匂いだ。ベッドには、高齢者が並んでいる。だが、彼はそこで初めて、理学療法士としての「熱」を取り戻した。
寝たきりの患者を起こす。座らせる。生活に光を当てる。目の前の患者は、手をかければ確実に応えてくれる。院長の理解もあり、彼は臨床に没頭した。
しかし、現場に沈潜し、地道にデータを積み上げていく中で、ある一つの『事実』が浮かび上がってきた。
「寝たきりの9割は、
適切な介入があれば防げたはずだった」
数字は残酷だった。目の前の患者を救うことに、嘘はない。だが、一人を家に帰しても、また一人、悪くなって運ばれてくる。そのサイクルを目の当たりにした時、鶯氏の脳裏に、ある光景がフラッシュバックした。
「言葉は悪いですが、ふと、自分たちがやっていることが『川下で流れてくる人を必死に引き上げている作業』のように思えてしまったんです」
川下での救助は尊い。しかし、川上から次々と人が流れてくる現状を止めなければ、悲劇は永遠に終わらない。なぜ、川上で止めないのか。なぜ、病気になる前の段階で関われないのか。 臨床にのめり込むほど、その問いは鋭さを増し、棘となって彼を苛んだ。
あれから約40年。時代は令和になり、仕組みは整った。だが、状況は好転したのか。
── 先生が理学療法士になられた1986年から現在まで、ずっと「予防」の重要性は叫ばれ続けてきました。40年近く経って、何が変わり、何が変わっていないと感じますか。
鶯氏: 変わったのは、制度という「器」です。介護保険ができ、地域包括ケアという言葉ができ、通いの場のような「仕組み」は全国に作られました。 しかし、変わっていないのは「中身」かもしれません。 病院に入院してくる患者さんは、相変わらず多い。地域で防げたはずの骨折や廃用で、病院が埋まっている。つまり、本質的にはまだ、我々は川下に留まったままで、川上へのアプローチが十分に届いていないように感じます。
── なぜ、形はできても中身が伴わないのでしょうか。
鶯氏:「やりっぱなし」になりがちだからです。体操教室を開き、指導をした。それで「予防をやった」ことになってしまう。 しかし、その介入が本当に効果を出しているのか、継続されているのか。そこまでの検証が不十分なまま、指導だけが増えている印象があります。 3日坊主で終わってしまっては意味がない。私が今、これほどデータにこだわる理由はそこにあります。「なんとなく良いこと」で終わらせず、検証して、修正していく。そのサイクルを回さない限り、状況は変わらないと思うのです。
30万円の説得力
情熱だけで、歴史は変わらなかった。だから鶯氏は、周到な準備のもと「計算式」を持ち出した。彼が提示したのは、鳴門市と三菱総合研究所と共同で解析したビッグデータだ。「通いの場」に参加する高齢者と、そうでない高齢者の医療・介護費を追跡比較したものである。
【鳴門市実証事業データ(60歳〜90歳対象)】
医療費抑制額
年間 約10万円
介護給付費抑制額
年間 約20万円
合計:年間 30万円 の社会保障費が浮く
「週に1回、外に出てみんなと体操をする。たったそれだけで、一人あたり年間30万円の社会保障費が浮く計算になります」
鶯氏は淡々と続ける。
「10人増えれば、300万円。100人参加者が増えれば、3000万円の節約になる。行政の方にこの数字を見せると、目の色が変わります」
数字は、嘘をつかない。3000万円という「事実」は、何百時間の情熱的な演説よりも雄弁に行政を説得した。結果、鳴門市では理学療法士が「リハ専門職」として雇用されるに至った。
「測って終わり」の罪
だが、金の話だけで終わるわけではない。鶯氏の視線は、現場の「質」に向けられている。 かつて、「重りを使った体操」の効果検証を行った際のことだ。開始から4ヶ月後までは数値が向上したが、8ヶ月後には改善が止まり、横ばいになってしまったデータがあった。
「なぜ改善が止まったのか。データを分析し、現場の声を聞く。参加者が『重りを増やすのが面倒だ』と、軽い負荷のまま続けていたことが分かりました。『過負荷の原則』が守られていなかったのです」
データを見なければ、「体操を続けているから大丈夫」と誤解していただろう。鶯氏は、そのデータを参加者に見せ、「このままでは筋肉がつかない」とフィードバックした。自分たちの状態を客観視した参加者たちは、そこで初めて行動を変え、再び数値は向上し始めたという。
データなき介入は、無責任だ。40年間変わらなかった川の流れを変えるには、精神論はいらない。必要なのは、事実に基づいた地道な検証と、修正のサイクルだけだ。
◇
「このまま、一生を終えるのか」──病院のポストは埋まり、先が見えない。閉塞感に覆われた若手たちの目は、副業や他職種への転職といった「外」の世界に向き、静かな人材流出が続いている。
答えは本当に「ここではないどこか」にあるのだろうか。迷える若手が、専門職としての誇りを捨てずに生き残るための「地図」。それは、意外にも足元にあった。後編では、鶯氏が示す「理学療法士の生存戦略」に迫る。
取材・文:今井俊太(POST編集部)