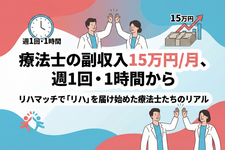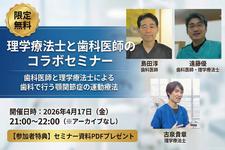杉並区議会議員の田中朝子氏は、2月19日の一般質問で「学校等における作業療法士の活用」について言及し、杉並区における支援の現状と今後の課題を指摘しました。本記事では、田中議員の発言や、過去に彼女が取り上げた「学校作業療法室」の導入事例をもとに、作業療法士に求められる新たな役割について考えます。
杉並区での作業療法士活用の現状と課題
杉並区では「自閉症・情緒障害特別支援学級」の設置が遅れており、発達障害のある児童生徒やその保護者の支援が十分に整っていない状況です。
田中議員はこの課題に対し、岡山県や岐阜県飛騨市で実施されている「学校作業療法室」や「学童保育と作業療法士の連携」などの事例を紹介し、杉並区でも作業療法士の積極的な活用を進めるべきだと提案しました。
区の回答としては、「作業療法士等専門職による学校の巡回支援体制を検討する」とし、乳幼児期からの発達支援の重要性も認識しているとのことですが、具体的な施策には至っていません。
「学校作業療法室」とは?
田中議員が以前のブログで取り上げた「学校作業療法室」は、作業療法士が学校内に常駐し、発達障害や運動機能に課題のある児童生徒に対して、感覚統合療法や運動療法を提供する取り組みです。
岐阜県飛騨市での事例
飛騨市では、2023年に「学校作業療法室」を試験的に導入し、学習や日常生活の困難を抱える子どもたちに対して、作業療法士が個別支援を行う体制を整えました。この取り組みは、学校教員や特別支援学級のスタッフと連携しながら進められており、以下のような効果が期待されています。
学習・生活動作の向上:字を書くのが苦手な児童への筆記補助や、集中力を高めるための環境調整
情緒面の安定:不安感が強い児童への感覚統合療法の提供
教師の負担軽減:特別支援教育を専門としない教員への助言やサポート
このように、学校作業療法室の導入は、児童の支援だけでなく、教員の負担軽減や学校全体の支援体制強化にもつながるとされています。
作業療法士が学校現場で果たす役割
学校作業療法室の事例や田中議員の提言を踏まえると、作業療法士が学校現場で果たすべき役割は多岐にわたります。
① 感覚統合・運動機能の支援
・運動発達が遅れている児童に対するトレーニング
・手先が不器用な児童への筆記・工作のサポート
② 学習支援・注意力向上
・ADHDなど注意欠如多動症の児童への集中力向上プログラム
・教室内での適切な環境調整(座席配置や感覚刺激の調整)
③ 教員・保護者への支援
・児童への適切な指導方法のアドバイス
・家庭での支援方法の提案
まとめ
杉並区での議論は、全国的に学校作業療法室を広げる契機となるかもしれません。現在、特別支援学級の設置が遅れている地域でも、作業療法士が学校や学童保育に関与することで、児童への支援の質を向上させる可能性があります。作業療法士として、教育現場での役割をどのように発展させるかは、今後の重要なテーマとなるでしょう。今後の杉並区での動向を注視しながら、作業療法士がどのように社会に貢献できるかを考えていきましょう。
杉並区議会録画配信▶︎https://suginami.gijiroku.com/voices/g07_Video_View.asp?SrchID=9502(8’15”頃から)
【合わせて読む】