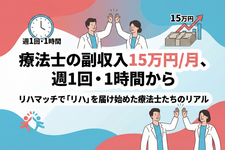月4日、参議院の「消費者問題に関する特別委員会」にて、理学療法士でもある自由民主党・田中まさし議員が質疑に立ち、高齢者・障害者の消費者トラブル、葬儀サービスに関する広告問題、そして感染症を含む遺体取扱いに関する制度整備の必要性について問いかけました。
本記事では、質疑の要点をまとめるとともに、田中議員と政府関係者とのやりとりを全文掲載します。消費者保護を強化するために何が必要か、その現場感と政策課題が浮き彫りになった議論です。
高齢者・障害者の消費者被害:2023年の被害額は10兆円超
冒頭、田中議員は2023年の消費者被害が契約購入金額ベースで「10.6兆円」、実際の支払額が「8.8兆円」にのぼると指摘。2020年比で約2.9兆円の増加となっており、深刻化する消費者トラブルの現状を訴えました。
特に、65歳以上の高齢者による相談は全体の30.5%。訪問販売や電話勧誘を受ける70代・80代の割合が高く、被害に遭っても「自分が悪い」と相談に至らない傾向もあるとのこと。認知症の高齢者に限れば、実際に相談できたのはわずか2割にとどまるといいます。
障害者も同様で、相談に至る割合は全体の5割。田中議員は「被害があっても声が上げられない構造的問題がある」とし、介護・訪問看護など支援職種との連携による見守り体制の強化を提案しました。
葬儀サービスの「7万円広告」が150万円に? 表示と実態のギャップ
次に取り上げられたのは、葬儀に関する消費者トラブルです。田中議員は、「7万円から」と広告されていた葬儀費用が、最終的に150万円以上請求された事例を紹介。特に、冷静な判断が難しい喪主が急いで契約するケースにおいて、「実際にはオプションが次々に追加され、高額になる」構造が問題であると指摘しました。
これに対し、消費者庁の大原審議官は、2023年度に寄せられた葬儀関連の相談件数が886件、2024年度は911件に達していると説明。不適切な表示に対しては景品表示法に基づき「措置命令などの対応を行っている」と明言しました。
ご遺体の取り違えや管理不足への懸念──夏にガイドライン策定へ
最後に議論は、感染症等で亡くなった遺体の取り扱いや、葬儀業者による管理体制の実態へと移りました。
田中議員は、「ドライアイス使用時の二酸化炭素濃度が管理されず、死亡事故につながった例もある」と述べ、現場での衛生・安全管理の基準整備を求めました。
厚生労働省の宮本審議官は、令和4~5年度の調査結果をもとに「56%の事業者が遺体取扱いに関する基準や手順を持っていない」とし、公衆衛生の観点から2025年夏を目途にガイドラインを策定中であると回答。保管方法やエンバーミング、搬送、温湿度管理といった具体的項目が盛り込まれる予定です。
田中議員は「消費者は事業者が適切に管理していると思っている。ガイドラインにとどまらず法制化も視野に検討を進めてほしい」と強調し、質疑を締めくくりました。
全文掲載
*一部修正。
高齢者・障害者の消費者被害について
田中まさし議員:自由民主党の田中まさしです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。早速質問に入りたいと思います。まず最初は、この消費者被害トラブルについてのご質問をさせていただきます。特に高齢者、障害者の消費者問題、消費者トラブルが非常に多くなっております。
消費者被害に関しましては、2023年契約購入金額ベースで10.6兆円、すでに支払った金額で8.8兆円という非常に高額のものになっております。これは2020年と比べて2.9兆円増加しており、由々しき問題であります。
令和6年度の消費者白書によりますと、2023年の消費生活相談のうち、65歳以上の高齢者が全体の30.5%を占めています。特に70代、80代の方では訪問販売や電話勧誘などの被害割合が非常に高く、他の年代よりも多くなっている状況です。
また、本人からの相談割合も注目すべき点です。高齢者全体では8割ですが、認知症の高齢者では2割にとどまり、被害が発生しても届出がなされないという状況が顕著です。判断能力の低下や、自責の念から相談に至らないという要因があると思われます。
障害者においても、本人からの相談割合は5割と低く、8割を占める全体と比較してもその差が明らかです。
2050年には、5世帯に1世帯が高齢者の単身世帯になると見込まれており、今後もこのような被害が増加していくことが懸念されます。そこで、消費者庁として高齢者や障害者への相談支援、被害防止にどのような取り組みを行ってきたのか、また今後、高齢者の増加に伴い訪問販売や電話勧誘販売による被害が拡大していくことが予想されますが、どのような対策を講じていくのかお伺いします。
伊東内閣特命担当大臣:田中議員には日頃より消費者行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
ただいまのご質問ですが、全国の消費生活センターに2023年に寄せられた消費生活相談のうち、高齢者に関するものは27万7千件、障害者に関するものは約2万4千件であり、総相談件数約90万件のうちの一定割合を占めております。
消費者庁としては、被害の未然防止および拡大防止に向けて、さまざまな注意喚起を実施しております。また、高齢者や障害者を対象とした見守り活動を行うため、見守りネットワークの設置を促進し、地域において福祉機関等と連携した取り組みを進めております。
悪質商法の被害については、関係省庁と連携を取りながら、特定商取引法違反の事案については法に基づいて厳正に対処しております。高齢者の消費者被害防止のための注意喚起も継続的に実施し、誰一人取り残されることなく安心して消費生活を送れるよう、消費者行政を推進してまいります。」
田中まさし議員:大臣、ありがとうございます。地域での支援ネットワークの充実は非常に重要であると考えております。
手口をある程度理解していれば未然に防げたというケースも多く、訪問介護や訪問看護など、日常的に高齢者の生活に関与している職種の方々とも連携し、未然防止やクーリングオフの迅速な対応につなげていただきたいと要望いたします。
葬儀サービスに関するトラブルについて
田中まさし議員:続きまして、この葬儀サービスに関するトラブルについて伺います。葬儀に関わる広告や費用に関するトラブルが依然として多く、高止まりしていると認識しております。
『追加費用なし』と広告されていたにもかかわらず、実際には追加費用が発生して高額な請求が行われるケースもあると聞いておりますが、消費者庁としてこのような葬儀サービスに関するトラブルをどのように把握されているのか、現状をお聞かせください。
大原審議官:お答え申し上げます。全国の消費生活センターに寄せられた葬儀サービスに関する相談件数は、2023年度に886件、2024年度には911件となっております。
具体的な相談内容としては、ホームページで見た料金と実際の請求額が異なる事例、よく説明されないままオプションを付けられたケース、また『きれいな寺』での葬儀を申し込んだのに実際は古い寺だった、などのトラブルが寄せられております。」
田中まさし議員:ありがとうございます。一般の方にとって葬儀は頻繁に経験するものではなく、多くの方が葬儀業者にはコンプライアンス意識を持ち、適切なサービスが提供されるものと信じて契約しています。
それにもかかわらず、契約内容と異なるサービスや費用が発生することは極めて重大な問題です。人生の最終段階である葬儀は、尊厳を持って丁寧に行われるべきものであり、このような問題は未然に防がれる必要があります。
最近では病院で亡くなられた後に、直接葬儀会社に搬送されるケースが増えており、また家族葬など廉価なニーズも高まっています。しかしながら、オプションの追加や祭壇の仕様によって費用が複雑化しており、冷静な判断が難しい喪主の立場において、料金やサービスに対する理解が十分でないまま契約してしまうことが多いと感じます。
『葬儀費用が7万円から』とホームページに記載されていたにもかかわらず、最終的に150万円を超える請求がなされたという報告もあります。このような事例に対し、消費者庁はどのように対応しているのでしょうか。
田中審議官:お答えいたします。委員ご指摘のように、葬儀は準備期間が限られており、事前の情報収集が非常に重要です。これまでにも消費者庁および国民生活センターにおいて、複数人での打ち合わせ、見積書の確認、不明点の質問、必要に応じて消費者ホットライン188などへの相談を呼びかける注意喚起を行ってきました。
また、景品表示法において、事業者が提供する商品やサービスの取引条件について、実際よりも著しく有利であると誤認される表示は禁止されており、実際の葬儀サービスにおいても、オプション込みであるかのように表示されていたが、追加料金が発生したという事案に対しては、措置命令など法に基づき厳正に対処してまいりました。
引き続き、こうした事例に対し、適切な対応を行ってまいります。」
田中まさし議員:ありがとうございます。相談に上がっていない事例も多くあると推察されます。
消費生活センターなどを通じて、葬儀業者に対して見積書の提示や利用者の同意取得などを促す通知や要請をされていることと思いますが、葬儀業者の正確な数も把握しきれていない現状があります。
今後も、すべての事業者が適切なサービス提供を行えるよう、ガイドラインの徹底と監督の強化をお願いしたいと思います。
遺体取扱いのガイドラインについて
田中まさし議員:最後の質問になりますが、感染症によるご遺体が発生する場合において、適切な対応が求められると考えています。具体的には、ご遺体を安置する部屋の室温の管理、遺体の取り違え、火葬に関するミスなど、さまざまな問題が生じていると聞いています。
また、ドライアイスを使用したことによって二酸化炭素濃度が上昇し、適切な管理が行われなかった結果として死亡事故が発生したという事例もあります。
こうした問題を踏まえ、遺体の安置や搬送を行う事業者に対するガイドラインが本年夏ごろを目途に策定予定と伺っております。このガイドラインの方向性、盛り込むべき内容、事業者への周知方法、そして運用状況の把握について、厚生労働省としてどのようにお考えでしょうか。」
宮本審議官:お答え申し上げます。厚生労働省では、令和4年度および令和5年度に、公衆衛生の観点から葬儀業者によるご遺体の取扱い状況について調査を実施いたしました。
その結果、約56%の事業者が遺体の取扱いに関する基準や手順が存在しないと回答しており、適切な対応がなされていない可能性があることが明らかになりました。
こうした実態を受け、公衆衛生の観点から、2025年夏頃を目途に遺体を取り扱う事業者が遵守すべき一定の基準を盛り込んだガイドラインを策定する方向で検討を進めております。
このガイドラインには、遺体の保管方法、エンバーミング(生前の状態に近づける処置)、搬送方法、衛生管理、施設内の温度・湿度管理など、実務上のポイントを盛り込む予定です。
今後は、葬儀業界への周知徹底に加え、遵守状況を適切に把握するためのモニタリング手法についても検討を進めてまいります。」
田中まさし議員:ぜひ前向きに進めていただきたいと思います。ご遺体の管理に関する手順が存在しないという事業者が過半数というのは、消費者の感覚と大きくかけ離れており、強い問題意識を感じています。
ご遺体の保管方法、エンバーミング、搬送など、どれをとっても個人の尊厳に関わる重要なテーマです。こうした領域においても、法律による明確な管理がなされていないという実態は大きな課題です。
消費者が安心して故人を見送ることができるよう、ガイドラインの策定はもちろん、必要に応じた法制化も含めた検討をお願い申し上げます。ありがとうございました。