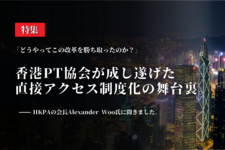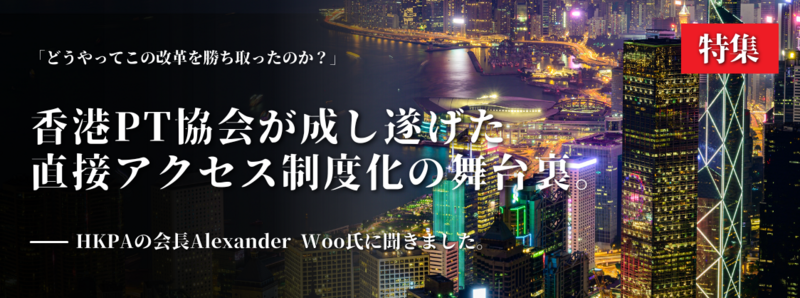
目次
- はじめに
- 独立開業型PT制度の存在
- 7年間の戦略的アプローチの全体像
- 科学的根拠が支えた制度導入
- 国際支援による信頼性の強化
- 各国における理学療法制度の比較(直接アクセス・財政・教育・国際連携)
- 日本との比較と示唆:同じ戦略でも結果が違う理由
- 日本との比較:単純な移植は難しい理由
- 「改革できない」のではなく、「改革の優先順位が問われている」
- 日本の制度改革は「財政」と「合意形成」のジレンマの中にある
- おわりに
- 謝辞
- 参考文献
はじめに
2025年7月、香港で理学療法士(PT)と作業療法士(OT)による患者の直接アクセス(ダイレクトアクセス)が条件付きで認められました。この歴史的な制度改革は、香港理学療法士協会(HKPA)が7年にわたって積み上げた戦略的アドボカシーの成果です[1]。
以前の記事でもこの法改正を速報的に伝えたが、読者からは「どうやってこの改革を勝ち取ったのか?」「反対勢力はなかったのか?」という声が多く寄せられました。この疑問に対し、本記事では、HKPAの会長Alexander Woo氏からの直接の助言や確認情報をもとに、香港における制度化のプロセスとその背景を詳しく解説します。単純な比較では語れない理由についても考察します。
独立開業型PT制度の存在
香港では法改正前からPTが「独立開業」できる制度が存在しました。これは、日本では法的にも制度的にも認められていない大きな違いです[2]。
たとえば、自らのクリニックを開業していても、多くの保険プランでは「医師の紹介がなければ理学療法費用を支払わない」とされ、事実上紹介なしでサービスを提供するのはレアでした。
7年間の戦略的アプローチの全体像
今回の法改正の意義
2025年の法改正は「どのような条件で、どのような際に、紹介なしで理学療法が可能か」を刑法上で明文化したもので、 社会的・経済的に正当性のあるルートを開く画期的な変化でした。
準備期間(2014年以前〜2018年)
HKPAは1978年からWorld Physiotherapyの加盟団体として国際的なネットワークを築いてきた。この土台が後のロビー活動にも大きく貢献した。
第1段階:問題提起と世論形成(2018〜2021年)
-
メディア戦略:患者の待機時間短縮、医療費削減などのメリットを可視化
-
政策提言:政府へ継続的に要望
■ 調査と世論形成の実際──数値が政策を動かした
HKPAは2019年から2021年にかけて、一般市民・慢性疼痛患者・在宅高齢者などを対象に複数回の調査を実施し、政策正当化の根拠を可視化しました[4]。
市民意識調査データ
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 紹介状なしで理学療法を受けたい | 68%が「ぜひ受けたい」「ある程度受けたい」と回答 |
| 医師紹介がなくても安全に受けられると思うか | 72%が「はい」 |
| 直接アクセスがあれば早く回復できたと思うか(既往患者) | 61%が「はい」 |
これらの結果は立法会の議員資料にも引用され、制度正当化の根拠となった。
教訓: 「市民の声」も、統計的に可視化・再構成することで政策対話に耐えるデータとなる。
第2段階:政策プロセスへの関与(2021〜2022年)
政策演説を受けて「修正紹介システム作業部会」が設立。HKPAが正式メンバーとして参加。
-
香港衛生局(Health Bureau)および一次医療委員会(Primary Healthcare Commission)との直接対話
-
学術機関、患者団体との協働による包括的アプローチ
-
一次医療における直接アクセスの設計図作成
-
エビデンスベースの提案資料準備
第3段階:立法プロセスでの対応(2023〜2025年)
■ 香港立法会でのプロセス──何が争点となり、どう乗り越えたか
HKPAは立法会法案委員会(Bills Committee)への働きかけを強化。
提出資料の構成:
-
World Physiotherapyの国際比較表
-
直接アクセス導入国の研究・エビデンス
-
保険会社との連携状況の報告
議員の懸念と対応
立法過程での懸念とHKPAの対応
| 懸念 | HKPAの対応 |
|---|---|
| 保険診療との整合性 | 民間保険会社の連携結果を提示 |
| 安全性への懸念 | 医療事故データや研修制度で説明 |
| 医師との分断 | 「12ヶ月以内の診察歴」の条件を提案 |
教訓:「制度が完全であること」よりも、「不安に丁寧に答え、段階的に導入する設計」が合意形成の鍵となる。
成果:2025年7月16日、補助医療専門職修正法案2025が可決。
Woo会長は「この制度は香港にとって患者ケアを大きく前進させる歴史的転換」と表現しています。
科学的根拠が支えた制度導入
導入の根拠としてHKPAが引用した主な研究例:
- Ojha et al. (2014):直接アクセスは治療効果・費用対効果ともに優れ、安全性への懸念も否定される[6]。
- Gallotti et al. (2023):筋骨格系疾患において医師紹介なしでも臨床アウトカムに差はなく、資源の最適化に寄与[7]。
ポイント:感情的な主張ではなく、国際的エビデンスを元にした説得が立法プロセスを前に進めました。
国際支援による信頼性の強化
- World Physiotherapyは「直接アクセスにふさわしい訓練と能力あり」として公式に支持[3]。
- Australian Physiotherapy Association(APA)も支援書簡・制度設計協力を提供[5]。
ポイント:複数国・複数団体からの支持は、「国際的に信頼される制度提案」であることの裏付けとなり、政治的な説得力を高めました。
各国における理学療法制度の比較(直接アクセス・財政・教育・国際連携)
本スライド表では、香港・日本・オーストラリアなど計8カ国における理学療法士制度の主要項目(直接アクセスの有無、財政方式、公的支出割合、保険給付制度、開業の可否、教育制度、国際連携状況)を視覚的に比較しています。各国の制度は歴史・文化・医療財政の違いに基づき多様化しており、本比較により制度設計上の特徴と相違点を把握できます。
※本比較は2025年時点の公的情報および各国協会発表に基づく内容です。詳細な法的定義や運用状況については各国の公式資料をご確認ください。
⇆横にスワイプして各国の制度を比較できます
香港
直接アクセス: 制度化(2025年・条件付き)
財政方式: 税+公立病院主導
公的支出比率: 約50〜60%(推定)
保険給付制度: 限定条件下で対応
開業制度: 認可済み(自由開業)
教育制度: 4年制+臨床(修士対応あり)
国際連携: WP・APAと連携
日本
直接アクセス: 未導入(医師指示必須)
財政方式: 社会保険方式
公的支出比率: 約80%(高齢化で逼迫)
保険給付制度: 医師指示下のみ点数化
開業制度: 制度的に不可
教育制度: 3年制専門学校〜4年制大学
国際連携: WP加盟(1982年〜)
台湾
直接アクセス: 未導入(制度改革中)
財政方式: 国家保険(NHIA)
公的支出比率: 約60〜70%
保険給付制度: 一部条件下で対応
開業制度: 医師紹介前提で可能
教育制度: DPT, BSc, 准学士の複合
国際連携: WP支援のもと法改正継続
シンガポール
直接アクセス: 一部可能(慢性疼痛等)
財政方式: 公私併用(Medisave等)
公的支出比率: 中程度
保険給付制度: 慢性疾患に限定対応
開業制度: 登録制度あり
教育制度: 4年制大学が基本
国際連携: 地域連携あり
韓国
直接アクセス: 不可(医師会の反対)
財政方式: 社会保険方式
公的支出比率: 約65〜75%
保険給付制度: 医師指示型制度のみ
開業制度: 法的に不可
教育制度: 4年制大学中心
国際連携: 制限的
オーストラリア
直接アクセス: 可能(1976年制度化)
財政方式: 税+保険(Medicare)
公的支出比率: 約70%
保険給付制度: 制度内で可能
開業制度: 自由開業可
教育制度: 修士課程中心(DPT含む)
国際連携: WP創設メンバー
デンマーク
直接アクセス: 実験的導入中
財政方式: 税方式(中央+地方)
公的支出比率: 約84%
保険給付制度: 地域によって段階導入
開業制度: 登録制で自由
教育制度: 学士+臨床主導
国際連携: 欧州モデルとして協調
タイ
直接アクセス: 一部可(保健省主導)
財政方式: 税方式(UHC)
公的支出比率: 高(30バーツ制度)
保険給付制度: 一部診療に限り可
開業制度: 地域許可制
教育制度: BScと一部修士課程
国際連携: ASEAN協調体制あり
日本との比較と示唆:同じ戦略でも結果が違う理由
日本理学療法士協会も類似の取り組みをしてきた
-
JPTAは長年にわたり診療報酬改定提案や政策提言、国際連携(WP加盟:1982年)を行っており、HKPAと同様の"努力"は行ってきた。
-
しかし、直接アクセスに関しては未実現。特に社会保障制度内での財源確保や医師会との協調設計が課題。
単純な比較では語れない3つの構造的要因
-
制度設計の前提条件が異なる
-
香港:開業型PTが制度上存在し、自由診療文化もある。
-
日本:すべてのPTが医師の指示下に属し、公的保険制度で一元管理。
-
-
医療財政の余力の違い
-
日本は高齢化と財政圧迫の中で、新規制度に予算をつけにくい。
-
保険点数新設のハードルは、専門職団体だけでは超えられない構造にある。
-
-
改革方針の方向性が定まらない
-
日本では「医師との役割分担をどうするか」「訪問リハ vs 医師管理」などで調整が難航。
-
制度導入の"合意形成モデル"が定まっていない。
-
日本との比較:単純な移植は難しい理由
香港やシンガポールなどが制度改革を進める中で、「なぜ日本ではできないのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。しかし、ここで重要なのは、各国の制度的・財政的な背景が大きく異なるという事実です。
社会保障と医療制度の三層構造が限界に
日本の社会保障制度は以下のような三層構造で構成されています:
-
年金制度(老齢・障害・遺族年金)
-
医療保険制度(国民健康保険、被用者保険など)
-
介護保険制度(2000年創設)
このうち医療と介護は高齢化の影響で支出が急増しており、持続可能性への懸念が強まっています。
日本の社会保障制度の現状(2023年)
| 指標 | 現状(2023年時点) |
|---|---|
| 医療費総額 | 約47兆円(過去最大) |
| 後期高齢者医療支出 | 約19兆円(医療費全体の約40%) |
| 社会保障給付費総額 | 約135兆円(国家予算の約2倍) |
| 一般財源からの繰入 | 年間10兆円超(赤字国債による補填も) |
こうした財政状況では、新たな制度(たとえばPTの独立診療に保険点数を付ける)を設計すること自体が、追加給付と見なされるため、非常に高いハードルとなります。
「改革できない」のではなく、「改革の優先順位が問われている」
香港で導入されたのは、あくまでも「段階的かつ条件付きの直接アクセス」です。一方日本では、PT/OTの診療行為には原則として医師の指示が必要であり、それに紐づく形で保険点数が設計されています。
また、日本ではすでに多くの理学療法士が医療・介護・福祉現場で制度内に組み込まれており、完全な制度外独立化が急務ではないという側面もあります。つまり、「制度が遅れている」というよりも、制度内でどう最適化していくかという設計の議論が滞っていると言えるでしょう。
日本の制度改革は「財政」と「合意形成」のジレンマの中にある
日本では「制度はあるが、それを最適化する意思決定ができない」という構造的課題が存在しています。
-
医療提供体制全体での役割分担と資源再配分が不明確
-
非医師専門職の活用:タスクシフティングへの抵抗と制度設計の不在
-
給付の追加か、再配分か:政治的コストを伴う改革が先送りされがち
こうした停滞構造の中では、理学療法士だけの問題ではなく、医療全体・社会保障全体の制度見直しと一体でなければ制度改革は困難です。
単なる"戦略の巧拙"ではなく、"制度の土壌"が異なる
香港と日本の違いは、「同じことをやったか否か」ではなく、「同じ土俵でやれるか」の問題に近い。香港モデルを日本に輸入する場合も、そのままコピーするのではなく、
-
段階的導入
-
公的制度内での限定導入
-
教育制度との接続
といった慎重な設計プロセスが求められる。
おわりに
香港理学療法士協会が実現した直接アクセス制度は、単なる医療制度改革ではありません。7年間にわたる多面的・段階的な戦略の積み重ねと、国際支援・世論・行政との関係性を丁寧に築いた末に得た成果です。
この事例は、他国の理学療法士や専門職団体にとって、"何をどう設計すれば制度が動くか"を考える実践的な参考モデルとなるでしょう。
謝辞
本記事の作成にあたっては、香港理学療法協会(HKPA)Alexander Woo会長より、多大なご協力をいただきました。制度化のプロセスに関する詳細な背景説明に加え、記事草稿に対する専門的なレビューと具体的なコメントを通じて、内容の正確性と現地文脈の理解に大きく寄与いただきました。HKPAが7年間かけて築いてきたアプローチの核心部分を、外部読者にも伝わる形に再構成するうえで、Woo氏のご助言は極めて重要でした。心より感謝申し上げます。
参考文献
- [1] Hong Kong Legislative Council (2025): LegCo Bills Committee Documents
- [2] HKPA Internal Reports on Private Practice and Insurance (2023–2025)
- [3] World Physiotherapy (2025): Support Letter to HKPA
- [4] HKPA: Public Opinion Surveys (2019–2021). Internal reports and submissions to the Legislative Council
- [5] Australian Physiotherapy Association: Collaboration Records (Provided by HKPA, 2023–2025)
- [6] Ojha HA, et al. (2014). Direct access compared with referred physical therapy: systematic review. Physical Therapy, 94(1):14–30.
- [7] Gallotti M, et al. (2023). Direct Access in Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review. J Clin Med, 12(18):5832.
- [8] Physiospot (2014). Direct Access to Physiotherapy in Hong Kong. Retrieved from: https://www.physiospot.com/2014/11/06/direct-access-to-physiotherapy-in-hong-kong/
- [9] Hong Kong Physiotherapy Association (2021). Response to Policy Address. Retrieved from: https://www.hongkongpa.com.hk/wp-content/uploads/2021/10/repsonse_policy_address_final.pdf
- [10] Hong Kong Physiotherapy Association (2022). Update on PT Direct Access – Dec 2022. Retrieved from: https://www.hongkongpa.com.hk/wp-content/uploads/2022/12/Update-on-PT-DA-28-Dec-2022.pdf
- [11] Hong Kong Legislative Council (2025). Bills Committee Papers on SMP Amendment Bill 2025. Retrieved from: https://www.legco.gov.hk/yr2025/english/bc/bc107/papers/bc10720250513cb3-643-23-e.pdf
- [12] World Physiotherapy (2025). Hong Kong Physiotherapy Association Celebrates Breakthrough Direct Access Legislation. Retrieved from: https://world.physio/news/hong-kong-physiotherapy-association-celebrates-breakthrough-direct-access-legislation
医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアの創業を経て、これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。
近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。