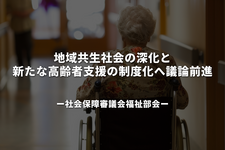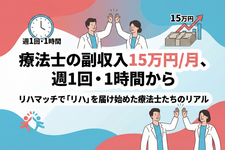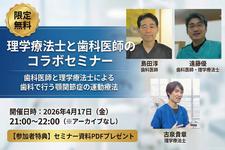社会保障審議会福祉部会の第31回会合が11月17日に開催され、地域共生社会のさらなる展開、身寄りのない高齢者への支援、社会福祉法人制度、災害に備えた福祉的支援体制、共同募金事業の在り方など、5つの主要項目について議論が行われました。会議は菊池馨実部会長(早稲田大学教授)の進行で進められ、事務局からこれまでの議論を踏まえた論点整理と検討方向性が示されました。
過疎地域での支援体制強化 柔軟な配置基準とAIの活用も検討
地域共生社会の推進では、市町村・都道府県の関係者で構成されたワーキンググループでの意見を踏まえ、過疎地域等での包括的支援体制構築に向けた新たな仕組みが示されました。
地域共生社会推進室長は「配置基準を柔軟にしてほしい」「窓口設置方法を自治体が選択できるようにすべき」という現場からの強い意見を紹介し、相談支援では分野横断で対応する相談員の研修の充実、AIの導入を含むモデル事業の検討方針を説明しました。
委員からは、地域住民同士の支え合いを育む福祉教育の重要性や、社会福祉法人による公益的活動の評価など、地域づくりを担う人材育成の視点についても意見が出されました。
「身寄りのない高齢者」への新たな支援事業を提案 利用料の高額化に懸念も
会議の中心となったテーマの一つが、身寄りのない高齢者等への新たな支援制度です。日常生活支援、入院・入所手続き、死後事務などを担う第2種社会福祉事業として制度化する案が示されました。
事務局は、9月会合での「準備期間と丁寧な説明が不可欠」という意見を踏まえた対応を報告。利用料については「高額化しないように検討が必要」という委員意見も反映されました。
鳥田浩平委員(東京都社会福祉協議会 副会長・常務理事)**は、現行の日常生活自立支援事業が抱える課題を指摘し、「専門人材の安定的な確保には財源の裏付けが不可欠」と訴えました。また、利用者の多くが低所得であり、利用料の引き上げが支援の断絶につながる懸念を示しました。
社会福祉法第106条の3に基づき、包括的な支援体制の中に「身寄りのない高齢者等への支援」を明確に位置づける方向性も示されました。
介護保険部会の議論も紹介され、身寄りの有無に関わらず「実質的に支援が得られない人を排除しない」幅広い支援の考え方が確認されました。
社会福祉連携推進法人の役割拡大へ 第2種事業の実施を可能に
社会福祉法人制度の見直しでは、社会福祉連携推進法人による社会福祉事業の実施を可能とする検討方向性が示されました。
実施可能な範囲は、利用者の人権保護や継続性の観点から第2種社会福祉事業に限定し、第1種事業は対象外としています。
また、人口減少地域で不可欠な社会福祉事業を維持するため、社員法人間の土地・建物の貸付支援を可能にすることや、社会福祉法人の解散時に自治体が残余財産の帰属を受ける仕組みの整備も提案されました。
災害福祉支援体制を法制度に位置づけ DWAT登録制度の整備へ
能登半島地震への対応を踏まえ、災害時の福祉支援体制について議論が行われました。
福祉基盤課長は「全都道府県からDWATが派遣された」と謝意を述べ、平時からの体制づくりの重要性を強調。具体的には、
-
社会福祉法に防災との連携を規定
-
地域福祉計画に災害福祉項目を追加
-
DWAT登録制度の整備
-
研修・訓練の制度化
-
派遣元事業者への配慮義務
-
チーム員への秘密保持義務
などが検討項目として示されました。
委員からは、生活圏域単位でのDWAT育成や、地域住民と連携した訓練を求める意見も挙がりました。
共同募金事業の見直し 寄付募集禁止規定や準備金の使途を整理
共同募金事業については、歴史的役割の大きさを評価する意見が委員から示され、寄付募集禁止規定の見直しや準備金の使途拡大などの方向性が提示されました。
福祉人材確保では処遇改善が最大争点 委員の意見割れる「養成施設卒業者の国家試験義務化」
会合後半では、福祉人材確保専門委員会の議論も報告されました。
松原由美委員長(早稲田大学教授)は「処遇改善なくして人材確保なし」と強調し、過去20年間で介護人材が最も増え、離職率が産業平均以下に改善したことを説明しました。そのうえで「賃金引き上げは中間層の形成と内需拡大につながる」と述べ、積極的な投資を求めました。
一方、介護福祉士養成施設卒業者の国家試験義務付け(経過措置)については委員間で意見が分かれました。
-
及川ゆりこ委員(日本介護福祉士会会長)
「国民の信頼のため経過措置は早期終了すべき」と主張。 -
小笠原靖治委員(日本介護福祉士養成施設協会副会長)
「定員充足率は58.5%。延期しなければ地域から養成施設が失われる」と懸念を表明。 -
永井幸子委員(連合)
「国家資格の信頼確保のため延期すべきではない」と反対の立場を示しました。
地域共生社会の実現に向け次段階へ
今回の会合では、前回までの議論を整理し、制度化に向けた検討事項がより具体化しました。特に、
-
過疎地域での支援体制の構築
-
身寄りのない高齢者への新たな支援制度
-
連携推進法人による事業実施
-
災害時の福祉支援体制の法制化
-
福祉人材確保の改革
といった重要テーマで意見交換が進みました。
事務局は、今回出された多様な意見を踏まえ、さらに検討を深める方針です。