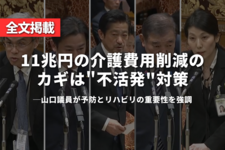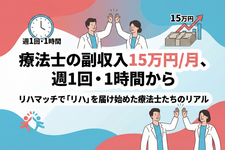21日、参議院予算委員会において、理学療法士でもある日本維新の会の山口和之議員が、循環器病対策と介護予防の重要性について質問を行いました。特に脳卒中や心臓病などの循環器疾患対策の予算拡充と、要介護度改善に向けた自立支援型介護の推進について、石破総理や福岡厚生労働大臣に見解を求めました。
議員の主張点
山口議員は以下の問題を中心に取り上げました.。
1.民間医療機関の経営危機:一般病院の医業利益率が2.3%の赤字状態であり、施設の建て替えや設備更新が困難な状況にあること
2.循環器病対策の重要性:脳卒中や心臓病などの循環器系疾患による医療費が全体の18.2%(約6兆円)を占めていること
3.がん対策と循環器病対策の予算格差:がん対策予算が351億円に対し、循環器病対策は44億円と大きな差があること
4.介護費用削減のための自立支援:不活発による機能低下が要介護度悪化の主要因であり、適切な介護とリハビリテーションで改善可能であること
循環器病対策の予算拡充を要請
山口議員は2018年に成立した「循環器病対策基本法」の重要性を強調し、がん対策と比較して明らかに少ない循環器病対策予算の拡充を求めました。特に予防やリハビリテーションの充実によって、医療費や介護費の削減につながると指摘しました。
これに対し石破総理は「予算については補正予算も活用して必要な額を確保している」としつつ、「循環器病の予防や正しい知識の普及啓発をさらに重視していきたい」と回答しました。
【循環器病対策基本法に関連する記事】
#01 脳卒中予防義務教育化に向けて|日本脳卒中協会 専務理事 中山 博文先生
#02 心不全パンデミックから脱却せよ! |日本循環器学会 代表理事 小室一成先生
#03 脳・循環器リハは、法成立後どう変わっていくのか|参議院議員 山口和之先生
#04 心不全パンデミック時代におけるセラピストの役割|北里大学 准教授 神谷 健太郎先生
自立支援型介護の推進
山口議員は、東日本大震災後に要介護者が増加した福島県の例を引き、「生活不活発」が要介護度悪化の主要因であると指摘。介護を「お世話型」から「自立支援型」へとパラダイムシフトさせる必要性を訴えました。
「老化や病気は避けられない。でも、不活発は“治せる”んです」。その一言に、リハビリテーション専門職としての信念が込められています。
また、全国展開するデイサービス事業所の事例として、要介護5の高齢者の66.7%、要介護4の高齢者の64.2%という高い改善率を紹介。川西市など自治体が取り組む要介護度改善インセンティブ制度の有効性についても言及しました。
石破総理は「近年高齢者の体力が向上している」と述べ、75〜84歳の要介護認定率が減少傾向にあることを指摘した上で、「高齢者が元気になりながら若い世代に負担をかけないことが重要」と応じました。
療法士の声が国を動かす時代
山口議員は質問の締めくくりとして、低栄養とリハビリテーションの重要性を指摘。介護保険法第4条の「国民の努力義務」について触れ、高齢者自身がどのようなサービスを受ければ状態が改善するのかを理解できていない現状を課題として挙げました。今回の質疑は、単なる予算配分の話にとどまりません。理学療法士が、政策決定の現場で、医療・介護の未来像を語る時代です。リハビリテーションの専門性が、今や社会保障の持続可能性に直結していることを、国会で示した山口議員の発言は、PT・OT・STにとって希望であり、行動の呼びかけでもあります。
全文掲載
*一部修正。
■ 山口和之議員(日本維新の会) 今回は、3月17日に同じ会派の青島健太議員が運動や活動によって医療費適正化と地域の取り組みについて質問を行いました。その続きとして、増大する医療・介護費用を効果的に抑制できないかという観点から、私も質問させていただきます。
その前に、本日午前中に石田委員や内越委員からも質問があった、経営が危機的状況にある民間医療機関についてお尋ねします。一見、医療費適正化と矛盾するように見えるかもしれませんが、民間医療機関も社会的インフラであり、命や健康を守るための医療機関や介護事業者が消滅してしまえば、社会が成り立ちません。
資料1をご覧ください。これは病院の医療利益率の年次推移で、医療福祉機構のデータです。緑が療養型病院、紫が精神科病院、赤が旧世紀の一般病院の利益率を示しています。特に赤い線の一般病院は、直近では2.3%の赤字で、ここ数年は赤字が続いています。
平均値なので、地方の患者数が少ない病院も含まれていますが、大学病院並みの救急搬送や手術件数、在院日数を維持していても、1%程度の利益しか上げられないのが現状です。倒産は免れたとしても、施設の建て替えや設備更新などへの投資は現実的に困難です。
今後、さらなる物価高や金利上昇が予想される中で、総理はどのようにお考えでしょうか。日本はかつて先進医療国と呼ばれていましたが、今の状況はその発展の妨げとなっていないでしょうか。総理は衆議院議員になる前に銀行勤務経験があると聞いています。この超低空飛行の医業利益率を、健全経営とお考えになりますか?

■ 石破内閣総理大臣 詳細については厚生労働大臣からも答弁します。私も4年間、銀行に勤務していましたが、病院に融資したことはなく、正確とは言えないかもしれません。
病院経営には様々なコストが関わります。医師、看護師、理学療法士、薬剤師などの給与体系、また、すべての病院にCTスキャンが必要かなど、さまざまな要素があります。診療報酬が経営の軸である中で、金融機関がどこまで予見可能性を評価できるかは課題です。
経営状況については、医療経済実態調査で把握し、その結果をもとに診療報酬改定を実施しました。さらに、補正予算により物価高騰や賃上げに対応する対策も講じています。今後も物価や賃金の動向を注視し、必要な対応を検討してまいります。
病院の資産価値についても検討が必要です。ホテルへの転用が困難な施設が多いため、政府としてもその特性を把握しつつ、診療報酬の水準について検討を進めたいと考えています。
■ 山口議員 では、厚生労働大臣に伺います。令和7年度の予算を執行した場合、病院の利益率はどうなると試算されていますか? このままでは、病院の経営は危機的状況に陥るのではないでしょうか。そのための支援策について伺いたいと思います。
■ 福岡厚生労働大臣 令和6年度診療報酬改定において、一定の措置を講じ、また昨年の補正予算で約1,300億円の支援パッケージを盛り込みました。さらに、令和7年度予算案では、入院時の食費基準の引き上げを行う予定です。
こうした措置を着実に現場へ届けることが重要です。病院経営は患者数や人件費の動向にも左右されるため、利益率の詳細な予測は難しいですが、補正予算の効果を把握した上で、適切な対応を進めてまいります。
■ 山口議員次のテーマに移ります。日本は世界に先駆けて超高齢社会となりました。ネガティブに語られがちですが、裏を返せば世界の先頭に立って課題を克服し、より優れた国となる絶好の機会です。
このパネル(資料2)は、内閣官房によるアジア諸国の高齢化の推移と、2035年の高齢者向け市場の推計です。高齢者向け市場には、医療・介護産業やそれに関連する生活産業が含まれ、2035年には約500兆円規模になると予想されています。日本がこの分野でリーダーシップを取ることは、国益に資するものであり、課題解決に向けた予防・医療・介護の充実は不可欠です。
資料3をご覧ください。我が国の疾病分類別医療費において、脳卒中・心疾患などの循環器系疾患による医療費は約6兆円、全体の18.2%を占めています。がん対策と同様に、極めて重要な領域です。
総理は高額療養費制度の見直しを行いました。医療・介護給付費の状況を踏まえ、脳卒中・心疾患などの対策がいかに重要かは明白です。質問いたします。
脳卒中や心疾患は予防可能な疾患であり、発症しても治療技術やリハビリによって回復が可能です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが関与するリハビリテーションにより、医療・介護費の抑制と、患者の社会復帰を実現できます。
2018年に成立した「循環器病対策基本法」は、私も超党派の議員の一人として関わりました。世界に誇る法律であると確信しております。私は昨年、参議院に繰り上げ当選し、再びこの法律の進捗を見届ける立場になりました。総理、この法律の重要性をどう認識されていますか?
■ 石破総理 議員がご関与されたこの法律は、平成30年に議員立法で成立した重要な法令です。脳卒中や心疾患は、死亡や介護の主因であり、予防から急性期、リハビリ、慢性期に至るまで一体的な対策が必要です。
循環器病による年齢調整死亡率は、コロナ禍を除けば男女ともに減少傾向にあります。今後もその重要性は高まると考えています。
この法律に基づき、推進基本計画を策定し、予防や知識の普及、医療・福祉サービス体制の整備、研究推進を計画的に進めています。
■ 山口議員 がん対策と比較した場合の、循環器病対策の予算について伺います。令和7年度の予算案では、どうなっているでしょうか。
■ 福岡厚労大臣 令和7年度当初予算案では、脳卒中・心疾患など循環器病対策に44億円を計上しています。第2期推進基本計画に基づき、普及啓発、地域支援体制構築、研究推進などの経費を確保しております。
■ 山口議員 ありがとうございます。では、がん対策の予算額はいかがでしょうか。
■ 福岡厚生労働大臣 令和7年度予算案におけるがん対策費は351億円となっております。
■ 山口議員 ご回答ありがとうございます。351億円と44億円。この差はあまりにも大きく、循環器病対策予算が見劣りする印象は否めません。
厚労省や国立循環器病センターにおいて、今後どのように取り組みを加速させていくのか、お聞かせください。
■ 大坪裕子 健康・生活衛生局長(厚生労働省) 第2期循環器病対策推進基本計画に基づき、予防・知識普及、医療福祉体制の整備、研究推進の3本柱で取り組んでいます。
また、国立循環器病研究センターでは、令和3年に循環器病対策情報センターを設置。診療情報収集や医療DXを踏まえたデータ活用の検討を進めており、今後も連携して対策を強化してまいります。
■ 山口議員 いずれにしても、がんと並んで重要な疾患群であり、循環器病の予防・研究・介入に注力することで、医療・介護費の削減にもつながるはずです。予算の効果検証を通じて、必要に応じて今後さらに取り組みを強化すべきです。
総理からも、この法律の趣旨を踏まえた今後のご決意を伺います。
■ 石破総理 (福岡大臣の答弁を踏まえ)政府として、健康寿命の延伸や医療・介護費負担の軽減に資するよう、循環器病の予防、知識普及、生活習慣改善の促進をさらに重視してまいります。
■ 山口議員 しっかりと成果を比較・検証し、不十分であれば追加的な対策を講じていただきたいと思います。
続いて、増大する介護費用を削減できないかという観点で質問いたします。
私は福島県出身です。14年前の東日本大震災の際、要介護者やその要介護度が重度化した高齢者が大幅に増加しました。その原因について、厚労省の見解を簡潔にお願いします。
■ 黒田秀郎 老健局長(厚生労働省) 福島県内の被災15市町村に関し、平成26年度に調査研究事業を実施しました。
2011年および2014年1月の介護保険事業状況報告月報データを用いた分析では、前期・後期高齢者ともに要支援・要介護1の認定者が増加し、さらに後期高齢者では要介護2〜3の増加も確認されました。
特定要因の分析には至りませんでしたが、報告書では、原子力災害による避難が要介護認定率の上昇に影響を与えた可能性が高いとされています。生活不活発やうつ傾向が要因の一つとして示唆されています。
■ 山口議員 おっしゃる通りです。生活不活発、いわゆる"不活発病"の重要性は非常に高いと考えます。
令和4年度の介護費用は約11兆円に上ります。資料4をご覧ください。これは介護が必要となった主な原因の構成割合を示したもので、循環器病、認知症、高齢による衰弱、骨折・転倒、関節疾患などが上位を占めています。多くが運動器、すなわち身体活動に関連しています。
高齢者が介護を必要とする原因と、その後の重度化の流れを示したイメージ図です。過齢による老化、病気、そして不活発が重なって介護が重度化していきます。
福島の事例でも、避難生活によって活動量が減り、不活発が増加し、結果として要介護度が重くなったと考えられます。これは全国の介護現場でも起こりうる問題です。
特に"座りっぱなし"の生活は、かつての"寝たきり"と同様に、活動量低下の原因です。介護施設では車椅子や椅子に座ったままの高齢者が多く見られます。実は、座っているだけの時間も、寝ているのと同程度に活動量が低いのです。
つまり、立つ・歩く機会が失われれば、それだけで介護量が一気に増える可能性があります。不活発は老化や病気と違い、“治せる要因”です。したがって、介護費用を抑えるには、不活発の改善が極めて重要です。
この点について、厚労省として、要介護度の改善率の推移をどのように把握しているのか、お伺いします。

■ 黒田秀郎 老健局長 介護給付費等実態統計に基づき、年度開始時点と終了時点での1年間の要介護度の変化(軽度化した人の割合)を把握しています。
令和5年度のデータでは、要介護度によって差はありますが、改善率は約3%〜13%の範囲です。
■ 山口議員 以前、我が党の東徹議員が要介護度の推移を尋ねた際、「推移を示すデータがない」との答弁がありました。今回も明確な推移データは示されていません。
データがなければ、政策がうまくいっているのか、日本の介護制度がどの方向に向かっているのかすら判断できません。数字がなければ評価も改善もできないのです。
2016年、当時の安倍総理は「介護におけるパラダイムシフト」を提言しました。「お世話型」から「自立支援型」へと移行し、要介護度の改善を目指すべきだという理念です。
しかし、そこから何年も経過しているにもかかわらず、要介護度の改善率や全国的推移は十分に可視化されていません。今後の政策評価のためにも、全国的な推移データの整備を強く求めます。
次に、兵庫県に本社を置く全国70カ所以上のデイサービスを展開する企業の事例を紹介します。代表者は元・心臓血管外科医で、家族の介護を通じてリハビリや介護の重要性を認識し、この事業に取り組んでいます。
この事業所では、栄養・水分補給に配慮しつつ、日常生活での活動を支援する自立支援型介護プログラムを提供。2023年度の成績では、要介護5の改善率66.7%、要介護4で64.2%、要介護3で47.7%という驚異的な数値が報告されています。
重度の要介護者ほど、不活発の要素を取り除ける可能性が高く、改善が期待できるという証左です。
このような介護現場を支える人材は、しばしば最低基準で配置されています。十分な人員や投資がなければ、自立支援のサイクルが機能せず、現場の努力が報われません。
これまでの「お世話型」から「自立支援型」への転換を本格的に進める必要があります。
資料をご覧ください。これは兵庫県川西市が導入した、要介護度改善に対するインセンティブ制度の概要です。2023年、この制度に参加した事業所の上位3位はいずれも、先述のデイサービス事業所が占めました。
日常生活動作(ADL)の改善率は98%に達し、制度の成果を示しています。
東京都も2023年から同様の制度を導入。介護保険料が全国一高い大阪市でも、横山博幸市長の指示で導入が検討されています。
「できないことを補う介護」から、「できるようにする介護」へ──自立支援型の介護が広がりつつある今、国としての支援体制強化が必要です。
総理にお伺いします。脳卒中・心疾患対策とともに、要介護度の改善や自立支援は、持続可能な社会保障の根幹です。世界に誇れる日本を実現するため、政府としてのご決意を伺います。
■ 石破総理 近年、高齢者の体力は向上しています。要介護認定率も、2015年から2023年にかけて、75〜79歳で1.3ポイント、80〜84歳で2.6ポイント減少しています。
ICTなどの技術を活用した予防・自立支援、そして高齢者の地域活動の推進が重要です。
加えて、介護現場の生産性向上や処遇改善は不可欠です。処遇を改善しなければ、この問題の解決は困難だと、委員会の審議を通じて痛感しております。今後も改善に努めてまいります。
■ 山口議員 余談になりますが、私の元勤務先である病院の外傷センターでは、大腿骨頸部骨折で搬送されてくる患者の半数以上が低栄養状態でした。タンパク質不足が主な要因であり、栄養とリハビリ、介護の連携が介護度の改善や健康寿命の延伸に直結します。
そこで、介護保険法第4条を確認したいと思います。
「国民は、自ら要介護状態になることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚し、常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態になった場合においては、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービスおよび福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」
しかしながら、問題はこの条文の存在を多くの高齢者が知らないという点にあります。どのようなサービスを受ければ、どのような改善が期待できるのかを理解していない方が多く、支援する側も日々の業務や加算取得、記録業務に追われているのが現状です。
その結果、車椅子の使用が常態化し、意図せずして活動量を制限してしまっている場合もあります。
今後、日本が世界の最先端のモデルケースとなれるよう、国としての積極的な情報提供と現場への支援をお願いしたいと思います。
以上です。