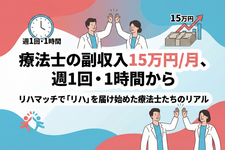高齢化社会が進行する中、健康寿命の延伸と生産年齢人口の減少という二重の課題に直面している日本。こうした状況に対し、これまで主に三次予防、すなわち実臨床でのリハビリテーションに関与してきた理学療法士(PT)・作業療法士(OT)が、地域や職域での一次・二次予防という“新たな領域”に踏み出そうとしています。
2024年度、PT協会とOT協会は「地域保健総合推進事業」の一環として、モデル事業に取り組む士会を対象に“伴走支援”という手法を導入しました。これにより、専門職自らが企画・実行する保健事業の立ち上げを支援し、地域・職域に根差した実践モデルを可視化することを目的としています。
"指導"ではなく"伴走"するという選択
この伴走支援は、従来のトップダウン型の支援とは一線を画します。支援者はあくまで“助言者”に徹し、現場のチームが自律的に計画・実行・評価までを担います。支援側は、必要なときに必要な情報やリソースを提供する存在にとどまります。認知症支援や共生社会の文脈で広がりを見せてきた「伴走支援」という概念を、保健事業に応用した点も注目されます。

出典:令和6年度 地域保健総合推進事業報告書(日本理学療法士協会・日本作業療法士協会)
山口と茨城、異なる地域での試行
モデルとして選ばれたのは、山口県PT会と茨城県OT会です。
山口県PT会は、企業への腰痛予防介入を実践し、
茨城県OT会は、メンタルヘルス不調対策をテーマに選定。県内リハビリテーション専門職協会との連携を視野に入れながら、出前講座の内容検討や、産業保健総合支援センターなど関係機関との連携窓口確立に注力しました。特に「健康経営」の視点を取り入れた戦略的アプローチが特徴で、単年度ではなく中長期計画として5年後を見据えたロードマップを作成しています。

出典:令和6年度 地域保健総合推進事業パンフレット(日本理学療法士協会・日本作業療法士協会)
研修会が映し出した現場のリアル
10月5日にはオンラインで研修会が開催され、全国から54名(PT 23名、OT 31名)の士会代表が参加。厚生労働省健康・生活衛生局、労働基準局、保険局からの講演をはじめ、実践報告やグループワークを通じて、現場の課題共有が行われました。
参加者アンケートでは、98%が研修会に満足と回答。一方で、事業に取り組めていない理由として、「情報不足」(66%)、「資金不足」(61%)、「設備不足」(58%)、「人材不足」(29%)などが挙げられ、これらの課題解決が今後の全国展開のカギとなります。
"健康経営"との親和性と、制度化への布石
この事業は、健康日本21(第三次)が掲げる「健康寿命の延伸」「健康格差の縮小」といった国の健康戦略と深く関連しています。特に「健康経営の推進」(目標:10万社)への寄与が期待されており、令和4年の「転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会」でも、理学療法士等による労働者の身体機能維持改善が有用と明記されています。
報告書では、事業の継続には「内向きの準備・調整」と「外向きの準備・調整」の両面が必要だと指摘されています。内向きには組織内での合意形成や人材育成、外向きには関係機関とのネットワーク構築や制度理解が重要です。
現場に求められる“しなやかさ”と“構造”
報告書では、支援の評価項目として「信頼関係」「自律性の尊重」「現実的な提案力」などが挙げられ、いずれも高く評価されました。重要なのは、指導ではなく“関係性”を軸にした支援が、制度や立場を越えて成果を生み出しうるという実践の証明であるという点です。
2025年度以降、伴走支援の全国展開も計画されています。ただし、現場での“しなやかさ”と、支援体制としての“構造”づくりが両立できなければ、継続的な成果にはつながりません。いま、PT・OTに求められているのは、専門性を武器に地域と職域の間に“橋”をかける視点です。
【訂正とお詫び】
本記事の初出時、「