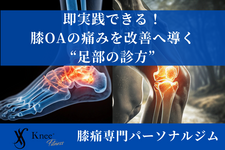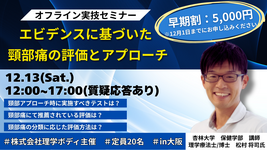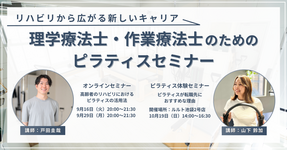9日、中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会(第72回)が開催され、「精神医療等の実施状況調査報告書(案)」について議論されました。この調査は2024年度診療報酬改定の影響を検証する目的で実施されました。本稿では特に精神科医療における作業療法士(OT)をはじめとするリハ専門職の配置状況に関するデータをまとめます。
作業療法士の配置率に見られる病棟間格差
病棟調査によると、OTが配置されている病棟は全体の51.7%となっています。ただし、この配置率は病棟の種類によって大きく異なります。精神科救急・合併症入院料を算定する病棟では66.7%と高い一方、精神療養病棟入院料を算定する病棟では25.5%にとどまっています。
この差は、急性期医療では回復促進のためにリハビリテーションが重視される一方、慢性期では人員配置の制約もあり、リハビリ専門職の配置が十分でない現状を反映していると考えられます。

理学療法士・言語聴覚士の配置状況は不透明
OTに比べ、理学療法士(PT)や言語聴覚士(ST)の病棟配置状況については明確なデータが示されていません。報告書案では具体的な割合に言及されておらず、今後の詳細な分析が求められます。
また、STに関しては「支援指導の診療報酬評価の拡充を求める」自由意見も複数寄せられており、現場では十分に役割が認識されながらも制度上の評価が追いついていない現状が浮かび上がっています。
地域精神医療とリハビリ専門職
診療所調査では、常勤換算での平均職員数としてOTが0.8人、PTとSTがそれぞれ0.2人と、病院に比べて極めて少ない状況が明らかになりました。地域の精神科医療におけるリハビリテーション支援体制の強化が課題として浮かび上がっています。

退院支援における役割
調査では、退院調整を目的とした多職種カンファレンスへの参加状況も分析された。「作業療法士等リハ職」が参加している病棟は全体の42.2%だが、特に「精神科救急急性期医療入院料」病棟で88.2%、「精神科地域包括ケア病棟入院料」病棟では93.5%という高い数値が示された。
議事中には「退院支援におけるリハの積極的関与は、今後の地域生活支援の質を左右する要素」と評価され、特に作業療法士の生活行為支援スキルへの期待が寄せられていた。

精神科地域包括ケア病棟の届出が進まない要因
精神科地域包括ケア病棟入院料の届出が進まない主な理由として、「満たすことが難しい要件がある」が74.8%と報告されました。具体的には、「病棟の1日に看護を行う看護職員、OT、精神保健福祉士及び公認心理師の数が、常時、当該病棟の入院患者の数の13:1以上であること」と「措置入院患者等を除いた当該病棟の入院患者のうち7割以上が、入院した日から6月以内に退院し、自宅等へ移行すること」の2点が特に難しい要件として挙げられています。
専門職人材の確保が困難なことから、多くの医療機関が届出を断念している状況が明らかになりました。
児童思春期医療におけるリハビリ専門職
児童思春期の患者に対する支援に関しては、病院では作業療法士の関与が42.3%と一定の水準である一方、診療所では14.3%にとどまっています。言語聴覚士の関与も病院で3.8%、診療所で4.8%と限定的です。理学療法士については両方の医療機関でほとんど関与がない状況です。
児童思春期の精神医療における支援内容としては、病院では「不安障害・気分障害への対応」が80.8%と最も多く、診療所では「不登校・ひきこもりへの対応」が95.2%と最も多く報告されています。

今後の展望
今回の検証部会では、精神科医療におけるリハビリテーション専門職の配置状況と課題が明らかになりました。特に地域医療や児童思春期医療におけるリハビリ専門職の関与を促進することが、今後の精神医療の質向上に不可欠であることが示唆されています。厚労省からは「精神医療の質向上には、リハ専門職を含む多職種の連携が不可欠であり、今後の制度設計においても重要な論点」とのコメントもありました。
次回の検証部会では在宅医療の実施状況調査についても検討される予定です。精神科医療の地域移行を進める上で、病院から地域へと切れ目なく支援を提供するための体制整備が重要な課題となっています。
















.png)