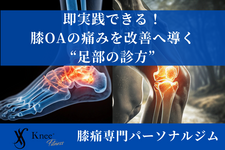24日、日本慢性期医療協会(日慢協)は定例記者会見を開催し、医療と介護を一体化したケアプラン構築を推進するための新たな取り組みとして「メディカルケアプランナー」の導入を提言しました。橋本会長は、ケアマネジメントの限界を踏まえたうえで、医療職が連携してプラン策定を支援する仕組みの必要性を強く訴えました。
寝たきりの重度化を防ぐために
冒頭では、要介護2〜3の高齢者のうち、1年以内に要介護4〜5に重度化する人の割合が17.8%に達しているというデータが示されました。これを半減できれば、月100億円規模の介護費の削減につながるとの推計もあり、重度化防止と機能改善の観点からケアプランの再設計が求められている現状が浮き彫りとなりました。

医療的視点をケアプランにどう組み込むか
日慢協ではこれまで、ケアマネジャーに医療的知識を付加する「メディカルケアマネジャー」の育成に取り組んできましたが、医療的判断を伴うケアプラン作成には限界があるとし、今回新たに医療職によるケアプラン支援「メディカルケアプランナー」構想を提起しました。
医師、看護師、リハビリ職、管理栄養士などの医療職がチームで退院患者の予後や生活支援の方針を整理し、ケアマネジャーと連携することで、より精度の高いプランが実現するとしています。

ケアマネジメントの限界と支援体制の再構築
現在、ケアマネジャー1人あたりの担当要介護者数は増加しており、業務過多や長時間労働、情報収集の困難さが深刻な課題です。特に病状や服薬、リハビリの予後など医療的判断が必要な場面では、十分な対応が困難となる場面も多く、こうした現場の負担を軽減する意味でも医療職による支援体制の整備は急務とされています。
加算制度よりも「仕組みそのもの」の整備が本質
メディカルケアプランナーという新しい機能に対しては、将来的に報酬体系上の加算が検討される可能性もありますが、会見では「加算の獲得」そのものが主目的ではないことが明確にされました。
橋本会長は、「加算があれば助かるが、それよりもこのシステムを社会に定着させることの方が重要」と強調。制度化より先に、医療・介護両面の視点をもつ仕組みを構築し、退院後の生活を支えるケアの質を高めていくことが先決であるとの考えを示しました。
ケアマネジャーの処遇改善も課題に
併せて、ケアマネジャーが処遇改善の対象となっていない現状についても問題視されました。日慢協は、ケアの司令塔ともいえるケアマネジャーの役割を重視し、待遇の見直しが制度的にも必要だと訴えています。
最適な連携体制の確立に向けて
医療職による情報提供とケアマネジメントの融合により、利用者本位のケア体制が整備されれば、重度化の防止だけでなく、介護の質の向上、介護職の負担軽減、さらには社会全体の介護費用削減にもつながると期待されています。
「寝たきりは防げる。そのためには今、現場をつなぐ新しい仕組みが必要だ」とする日慢協の提言は、今後の制度設計にも大きな影響を与える可能性があります。