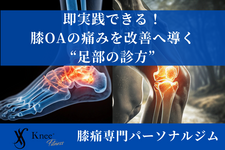入院・外来医療等の調査・評価分科会、リハビリテーション分野の課題を集中審議
6月26日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」では、2026年度診療報酬改定に向けたリハビリテーション分野の課題について集中的な議論が行われました。特に、退院後の生活を見据えた「院外リハビリ」の拡充、早期からのリハビリテーション介入、そして新たな概念として注目される「POC(Point of Care)リハビリ」の評価について、具体的なデータを基に検討が進められました。
院外リハビリの現状と課題、3単位制限の見直し求める声
現在、医療機関外でのリハビリテーションは、2016年度改定で「IADL(手段的日常生活活動)や社会生活における活動の能力獲得」を目的として、1日3単位まで疾患別リハビリテーション料での算定が認められています。しかし、厚生労働省が提示したデータによると、屋外等での疾患別リハビリテーションを実施した患者のうち、3単位を超えて実施した症例が45%に上ることが明らかになりました。
3単位を超える院外リハビリの具体的な内容としては、自宅内でのADL動作の評価・訓練、公共交通機関の利用、自宅での家事動作などが多く報告されています。
この現状を受けて、日本慢性期医療協会の井川誠一郎副会長は「院外リハビリを大胆に進められるような診療報酬改定が必要である」と発言。一方、健康保険組合連合会の中野惠参与は「生活機能向上にどれだけの効果があるのかを定量的に検証しながら考えていく必要がある」として、エビデンスに基づいた検討の重要性を指摘しました。

退院前訪問指導の実施率低迷、包括評価からの除外検討も
退院前訪問指導については、再入院・転倒の減少や退院後のADL向上に効果があることが文献で示されているものの、実施率の低迷が課題となっています。
厚労省のデータによると、回復期リハビリテーション病棟では退院前訪問指導料が包括評価されているものの、全入院患者の3~5%にとどまっています。また、退院前訪問指導を実施している病院の割合も14~24%と低い水準です。
実施体制については、95%以上の病棟で理学療法士、作業療法士が関与し、40%以上の病棟で看護師やその他職種が参加していることが分かりました。最も多い主担当者は作業療法士となっています。
全日本病院協会の津留英智常任理事は「回復期リハビリでは相当頑張って退院前訪問指導を実施している。その取り組みを踏まえた評価(包括評価からの除外と点数増など)を行えば、さらに実施が増えると考えられる」と提言しました。


高次脳機能障害者への支援体制に課題
特に高次脳機能障害者については、退院支援における複数の課題が指摘されました。関係機関へのヒアリング調査では、入院医療機関における高次脳機能障害の診断や説明の不足、支援に係る情報提供の不足、高齢患者の多い病棟における障害福祉関連機関とのネットワークの希薄さなどが明らかになっています。
津留委員は「高次脳機能障害者、とりわけ若い患者については、その後遺症を家族や職場に十分に理解してもらう必要があるが、まだ難しい。リハビリ医やリハビリ担当者と職場の産業医との連携をしっかり評価してはどうか」と具体的な連携強化策を提案しました。

早期リハビリ開始、38%が3日以内に介入できず
2024年度改定で新設された急性期リハビリテーション加算の算定状況を分析したところ、発症から3日以内に介入できていない割合が38%に上ることが判明しました。この背景には、現在の加算制度では「発症日からリハビリ開始までの日数」についての要件が設けられておらず、どのタイミングからでも算定可能となっていることが影響していると考えられます。
中野委員は「発症から3日以内の実施が多く、早期のリハビリ開始が極めて重要な点を意識した検討を進めるべき」と指摘。旭川赤十字病院の牧野憲一特別顧問・名誉院長は「土日のリハ実施状況なども絡めて分析していく必要がある」として、より詳細な分析の必要性を訴えました。

POCリハビリの評価、実施体制や効果の検証が課題
昨今注目を集めているPOC(Point of Care)リハビリについても議論されました。これは「患者の傍らで、20分未満の短時間ADL改善訓練を行う」もので、地域包括ケア推進病棟協会ではADL改善効果が高いというエビデンスが構築されつつあると報告されています。
しかし、20分未満の実施のため疾患別リハビリ料の評価対象とならず、現在は各病院が手弁当で実施している状況です。調査結果では、回復期リハビリ病棟1~4において「生活の場における短時間のリハビリテーション」を実施している病棟は1~2割程度にとどまっています。
中野委員は「リハビリ専門職種の実施が好ましいのか、病棟で看護師が実施しても効果が上がるものなのか、さらなる分析が必要である」と指摘。井川委員は「POCリハビリの評価が期待されるが、例えば実施した介入の内容記録などを求められれば現場の負担が過重になる点などを勘案した評価を行うべき」として、現場負担に配慮した制度設計の重要性を強調しました。



2026年改定に向けた検討方向性
これらの議論を踏まえ、2026年度診療報酬改定では以下の点が検討課題として浮上しています。
- 院外リハビリの単位数制限緩和と適応範囲の拡大
- 退院前訪問指導の評価充実と実施促進策
- 早期リハビリ開始要件の明確化
- POCリハビリの診療報酬上の位置づけ
- 高次脳機能障害者への退院支援体制強化
今後、これらの課題について、効果検証やエビデンスの蓄積を進めながら、具体的な診療報酬改定内容の検討が本格化していくことになります。特に、リハビリテーション分野においては、急性期から回復期、生活期まで切れ目のない支援体制の構築と、患者の生活の質向上に資する評価体系の確立が重要なテーマとなりそうです。