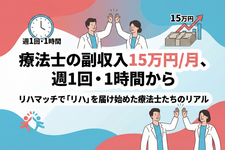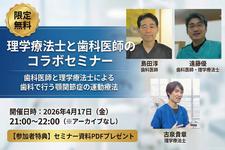2025年、日本循環器学会と日本心不全学会が共同で発表した「心不全診療ガイドライン2025年改訂版」は、心不全診療のあり方を大きく前進させる内容となりました。特に注目すべきは、急性期から在宅期までを包括する医療体制のなかで、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(PT・OT・ST)の役割がこれまで以上に明確に記された点です。
この記事では、ガイドライン改訂のポイントを、リハビリテーションや地域連携など、現場で働く療法士に関わりの深い視点から整理しました。
1. リハビリテーションの役割が明文化
今回の改訂では、心不全診療におけるリハビリテーションの重要性があらためて明示されました。特に、急性期から早期に介入することの意義が強調されており、「切れ目のないケア」の中核として、理学療法士の介入が不可欠であることが示されています。
日本国内で実施されたACTIVE-ADHF試験では、入院初期からの理学療法や有酸素運動が、患者の運動能力や認知機能、退院後のQOLに良い影響を与えることが確認されています。また、重症心不全患者に対しても、低強度の運動や筋トレが骨格筋機能の低下や運動耐容能の悪化を防ぐ可能性があるとされました。
実際のリハビリ内容についても、ストレッチング、バランス練習、ADL訓練、低強度の筋力トレーニングといった具体的な手技が記載されており、現場での指針となる内容が盛り込まれています。
2. ADL・QOL評価およびPROの導入
今回のガイドラインでは、「ADL(日常生活動作)」や「QOL(生活の質)」の評価が、単なる生活支援の尺度ではなく、心不全の予後を左右する要素として位置づけられました。
ADLの評価にはBarthel IndexやFIM、Katz Indexが活用され、患者の再入院リスクや死亡率との関係が示唆されています。加えて、KCCQやMLHFQといった質問紙によるPRO(患者報告アウトカム)の活用が推奨されており、治療の質向上や患者との対話促進に役立てられるとされています。
3. 身体機能評価の充実と歩行速度の導入
身体機能の定量的評価に関しても記述が進化しました。SPPB(Short Physical Performance Battery)や握力測定、歩行速度(特に1秒あたりの速度)は、今後の予後予測や治療計画の指標として活用される可能性があります。
中でも歩行速度は、従来の6分間歩行試験と同程度の有用性があるとされ、より簡便かつ客観的な評価ツールとして注目されています。
4. 移行期(脆弱期)ケアへの新たな着目
心不全患者が退院してからの90日間を“脆弱期(vulnerable phase)”と定義し、この期間に多職種で積極的に支援を行う必要性が示されました。このセクションの新設は、ガイドラインとしても画期的です。
移行期の支援には、理学療法を含む心臓リハビリテーション、服薬指導、訪問看護、栄養支援、ICT活用などが挙げられ、理学療法士が多職種連携の中核を担う場面が広がっています。J-PROOFやACTIVE-ADHFといった研究成果も、そのエビデンスとして活用されています。
5. 地域包括ケア・多職種連携・外来心リハ
ガイドラインでは、病院での治療だけでなく、地域での包括的な支援体制の構築が求められています。とりわけ、かかりつけ医や福祉・介護職と連携しながら、患者の生活全体を支える体制が重要視されています。
外来心リハの継続的実施や、地域包括ケアの推進、さらには多職種による外来でのフォローアップ体制の整備により、PT・OT・STの活躍の場はさらに広がることが期待されています。
6. デジタルヘルスと遠隔リハビリテーション
ICTやウェアラブルデバイスを活用した在宅支援や遠隔リハビリも、今後の心不全ケアの一つの柱として言及されています。
特に、退院後に医師と患者をつなぐ手段としての遠隔診療が再入院リスクの低減につながった例や、ウェアラブル機器を使った在宅運動療法がフレイル合併心不全患者の歩行能力を改善した事例などが紹介されています。
ただし、遠隔リハビリの導入には、IT環境の整備や人員体制、費用面の課題があることも忘れてはなりません。

まとめ
2025年改訂版の心不全ガイドラインは、PT・OT・STにとって新たなチャンスを提示するだけでなく、その専門性が医療の質を左右する重要な局面に差しかかっていることを示しています。
これからの心不全ケアは、病院の中だけで完結せず、地域や在宅、そしてICTを活用したケアへと広がり続けます。その中で、療法士一人ひとりがどう関わっていくかが、患者の人生を支える大きな力となるのです。
▶︎https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Kato.pdf