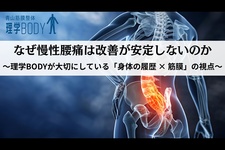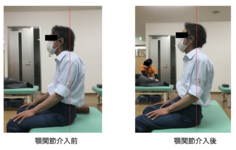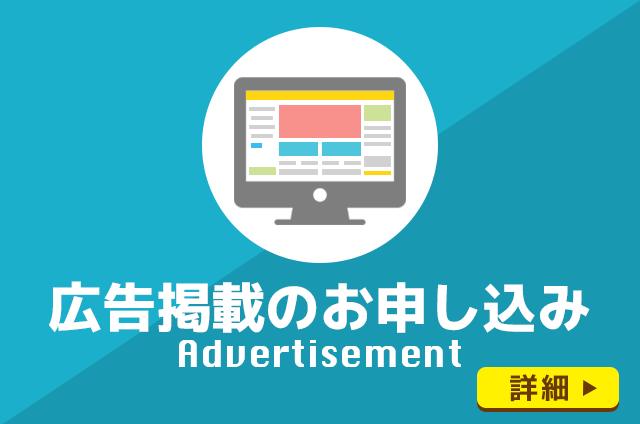運動麻痺重症例における麻痺側下肢運動機能の回復には、損傷半球に加えて非損傷半球を含めた補足運動野の機能が重要であるといわれています。近年では、経頭蓋直流電気刺激(tDCS)が、運動関連領野や皮質脊髄路の興奮性を高める手段として用いられていますが、非損傷半球を含めた補足運動野に対するtDCSが運動麻痺重症例における麻痺側下肢運動機能の回復へ及ぼす影響は明らかになっていません。宝塚リハビリテーション病院の大西 空氏(畿央大学 健康科学部 理学療法学科13期生)、畿央大学大学院 博士後期課程修了生の水田 直道氏(現・日本福祉大学)、森岡 周 教授らは、運動麻痺重症例1名に対して長下肢装具を用いた介助歩行と両側補足運動野へのtDCSを併用したトレーニングの効果について検証しました。
この研究成果は、Brain Sciences誌(Effects of Transcranial Direct Current Stimulation of Bilateral Supplementary Motor Area on the Lower Limb Motor Function in a Stroke Patient with Severe Motor Paralysis: A Case Study)に掲載されています。
研究概要
脳卒中後早期における運動麻痺の重症度は麻痺側下肢運動機能の回復に影響を与えますが、運動麻痺重症例においても、麻痺側下肢運動機能が比例回復以上に回復する患者も少なからず存在することがわかっています。一般的に、麻痺側下肢の運動機能を回復させるためには、下肢運動時に損傷半球の運動関連領野から出力される皮質脊髄路の興奮性を高めることが重要であるとされています。しかし、運動麻痺重症例においては、損傷半球の運動関連領野を起源とした皮質脊髄路の興奮性を増大させるには限りがあります。
近年、経頭蓋直流電気刺激(tDCS)が大脳皮質を非侵襲的に興奮させ運動関連領野や皮質脊髄路の興奮性を高める手段として用いられており、脳卒中患者に対しては損傷半球の一次運動野へのtDCSが皮質脊髄路の興奮性や麻痺側下肢筋力を増大させることが示されています。しかし、非損傷半球を含めたtDCSが麻痺側下肢の運動機能にどのような影響を与えるかは明らかになっていません。特に、運動麻痺重症例においては、非損傷側補足運動野の活性化が麻痺側下肢の運動機能回復に影響を与えるとされています。
そこで宝塚リハビリテーション病院の大西 空氏、畿央大学の森岡 周 教授らの研究グループは、運動麻痺重症例1名に対して長下肢装具(KAFO)を用いた介助歩行と両側補足運動野へのtDCSを併用したトレーニングが、20分後および4週間後における内側広筋の筋活動と筋間コヒーレンス(皮質脊髄路興奮性を反映)を増大させることを明らかにしました。
本研究のポイント
- 運動麻痺重症例1名を対象に、長下肢装具(KAFO)を用いた介助歩行と両側補足運動野へのtDCSを併用したトレーニングを4週間行うことで、介助歩行トレーニングのみを4週間行った時期に比べて、麻痺側内側広筋の筋活動と筋間コヒーレンスが増大しました。
- また、KAFOを用いた介助歩行と両側補足運動野に対するtDCSを20分間併用したトレーニングは、介助歩行のみを20分間行ったトレーニングや、介助歩行と損傷側補足運動野に対するtDCSを20分間併用したトレーニングに比べて、麻痺側内側広筋の筋活動と筋間コヒーレンスを即時的に増大させました。
研究内容
重症な運動麻痺を呈した脳卒中患者1名(Fugl-Meyer Assessmentの下肢シナジー項目0点)を対象に、後ろ向きABデザインを行いました。A期間ではKAFOを用いた介助歩行トレーニングのみを行い、B期間では介助歩行に両側補足運動野へのtDCS(bi-tDCS)を組み合わせたトレーニングを各4週間行いました。
また、bi-tDCSの即時的な影響も検証するために、両期における間の期間において、①20分間の介助歩行トレーニングのみ(tDCSなし)、②20分間の介助歩行に損傷側補足運動野へのtDCSを併用したトレーニング(uni-tDCS)、③20分間のbi-tDCSの3条件を実施しました(3条件はそれぞれ別日に実施し、トレーニング前と20分後における即時的な影響を比較)。測定は、内側広筋の筋活動および筋間コヒーレンスのβ帯域(皮質脊髄路の興奮性を反映)としました。

図1:患者の核磁気共鳴画像(MRI)
発症時のMRIでは左放線冠と内包後脚を中心とした広範囲領域に高信号反応を認めていました。

図2:介入プロトコル
A期では介助歩行トレーニングのみ(no-tDCS)、B期では介助歩行に両側補足運動野に対するtDCSを組み合わせたトレーニング(bi-tDCS)をそれぞれ4週間実施しました。また、A期とB期の間の期間(3日間)において、①―③の3条件における訓練前と20分後の即時効果を測定しました。

図3:tDCSの刺激部位の違いが麻痺側下肢運動機能へ与える即時的な影響
tDCSの刺激位置の違いによる内側広筋の筋活動(A)および筋間コヒーレンス(B)の即時的変化を示しています。グラフ内の数値は、訓練後の値を訓練前の値で割った値を示しています。筋活動の変化は、no-tDCSで1.0、uni-tDCSで1.0、bi-tDCSで1.2でした。また、筋間コヒーレンスの変化は、no-tDCSで1.0、uni-tDCSで1.1、bi-tDCSで1.2であり、共にbi-tDCSにおいて増大しました。

図4:4週間のbi-tDCSによる介入が麻痺性下肢運動機能に及ぼす影響
A期とB期における内側広筋の筋活動および筋間コヒーレンスの時系列データと各時期の変化量を示しています。(A, C)は、A期とB期を合わせた5時点における、内側広筋の筋活動および筋間コヒーレンスの値を示しています。濃い緑と濃い赤の線は生データを、薄い緑と薄い赤の破線はトレンド除去されたデータを示しています。(B, D)は、A期とB期における4週間の筋活動と筋間コヒーレンスの変化をそれぞれ合計したものです(正の値であるほどトレーニングによる改善が大きいことを示す)。筋活動はA期で-10.94、B期で9.2であり、B期で増大しました。また、筋間コヒーレンスはA期で-0.95(×10-1)、B期で0.52(×10-1)であり、B期で増大しました。
本研究の意義および今後の展開
本研究では、重症な運動麻痺を有する脳卒中患者を対象に、20分および4週間のbi-tDCS介入が、内側広筋の筋活動および皮質脊髄路の興奮性に及ぼす影響について検証しました。その結果、bi-tDCS介入は、20分後および4週間後における内側広筋の筋活動および筋間コヒーレンスを改善させました。今後は、より多くの症例を対象にして、非損傷半球運動関連領野を起源とした皮質脊髄路の興奮性増大が運動麻痺重症例における歩行能力の回復に及ぼす影響について検証する予定です。
論文情報
Sora Ohnishi, Naomichi Mizuta, Naruhito Hasui, Junji Taguchi, Tomoki Nakatani and Shu Morioka.
Brain Sciences, 2022, 12.4: 452.
詳細▶︎https://www.kio.ac.jp/topics_press/73599/
注)プレスリリースで紹介している論文の多くは、単に論文による最新の実験や分析等の成果報告に過ぎません。論文で報告された新たな知見が社会へ実装されるには、多くの場合、さらに研究や実証を進める必要があります。最新の研究成果の利用に際しては、専門家の指導を受けるなど十分配慮するようにしてください。