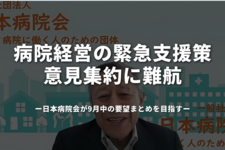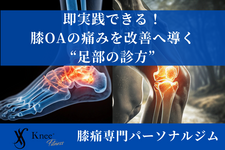日本病院会は26日、定例記者会見を開き、第3回常任理事会の報告を行った。藍澤会長は、2025年度中の病院経営支援として緊急的な財政措置について議論したものの、理事間で様々な意見が出て意見集約に至らなかったと明かした。同会では9月中に具体的な要望をまとめる方針を示している。
緊急支援策で意見分かれる
藍澤会長によると、理事会では病院の経営支援の必要性について議論したが、支援対象や方法論を巡って多様な意見が出た。「多くが赤字の病院を支援するということだが、全ての病院を対象にすると黒字の病院も支援することになるのではないか」といった指摘のほか、以下のような論点が挙がったという。
- 公的病院と民間病院の区別について
- 地域の救急医療拠点病院への重点支援
- 赤字・黒字ではなくキャッシュフロー基準での支援
- 一床当たりの支援方式への懸念(コロナ禍での問題を踏まえ)
- 収入支援より費用増加への対応
藍澤会長は「いずれももっともだと思う一方で、実施が難しい面もある」とし、「実際に議論を始めるとなかなか難しい。各病院の抱える経営課題が様々であることを改めて感じた」と述べた。
理事間でメール意見交換へ
意見集約の困難を受け、同会では理事会での議論に先立ち、各理事間でメールでの意見交換を行うことを決めた。藍澤会長は「遅くても次の理事会、9月中には具体的な要望をまとめなければならない」と述べ、早急な対応の必要性を強調した。
2025年経営調査、回答期限を延長
会見では2025年病院経営定期調査についても報告があった。事務局によると、4病院団体(日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会)が共同で実施しており、5149病院に調査を依頼している。
当初8月22日だった回答締切は9月19日まで延長された。現在、多くの病院からデータ提出があっているという。調査結果は9月中から10月初めにかけて取りまとめ、公表する予定。
急性期病院の構造的課題を指摘
質疑応答で急性期病院の経営難について問われた藍澤会長は、7対1病床を主体とする急性期病院の構造的問題を説明した。
「急性期病院は医療原価が高く、材料費と薬剤費の占める割合が大きい。薬剤費は診療報酬で適正に補填されているが、医療材料については補填されているものとされていないものがあり、使用量が増えれば持ち出しになる」と指摘。
手術機器の部品や腹腔鏡手術で使用する器具保持具など、新しい医療材料の登場と使用量増加が、急性期病院の赤字拡大の要因になっているとの見解を示した。
同会では、どの品目の使用が増加しているかや新規材料の動向について調査を行い、データ化して厚生労働省などに訴えていく方針を明らかにした。
理学療法士としての現場経験を経て、医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアを創業。これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。
近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。