Rehabilitation study group / workshop search 【for physiotherapists / occupational therapists / linguistic hearing professionals】
72件のセミナー

PT・OT・STが「離床」を基礎から実践まで深く理解するセミナー(オンラインセミナー)
離床は、臥床により生じる様々な悪影響を断ち切る最も基本的な医療介入です。 本セミナーでは、離床を解剖学的に、生理学的に、病理学的に解説します。離床に関わる全ての療法士が知っておくべき知識と理論で...

PT・OT・STのための医療統計セミナー(Webセミナー)
臨床の療法士が「情報を正確に読み解く」上で必要な統計の基礎知識は実は案外シンプルです。基本に従って段階的に、そして、自分の臨床経験に似たケーススタディを通じて学ぶことで統計の実用性が見えてきます。

PT・OT・STのための糖尿病を基礎から理解するセミナー(Webセミナー)
糖尿病はほぼ全ての臓器に悪影響を及ぼし、ほぼ全ての治療を阻害します。 PTもOTもSTも糖尿病を理解することを無視できません。本セミナーでは全ての療法士が知っておくべき糖尿病の知識を基礎から学びます。

2026年度診療報酬改定から見る訪問看護・訪問リハビリの実務ポイント(14日間の見逃し配信付き)
2026年3月25日(水)オンライセミナー

パーキンソン病のセルフケア・自主トレ指導~根拠から組み立てるリハビリメニューの考え方~(14日間の見逃し配信付き)
2026年3月23日(月)オンライセミナー

車椅子シーティング実技セミナー〜褥瘡・拘縮・呼吸・食事・姿勢への評価と実践〜
2026年3月22日(日)実技セミナー

訪問リハのプロになる第一歩! 制度・スキル・リスク管理を確実に押さえる(14日間の見逃し配信付き)
2026年3月16日(月)オンライセミナー

イチから学ぶリハビリ部門管理者のマーケティング 〜地域No.1の組織を目指そう〜(14日間の見逃し配信付き)
2026年3月14日(土)オンライセミナー
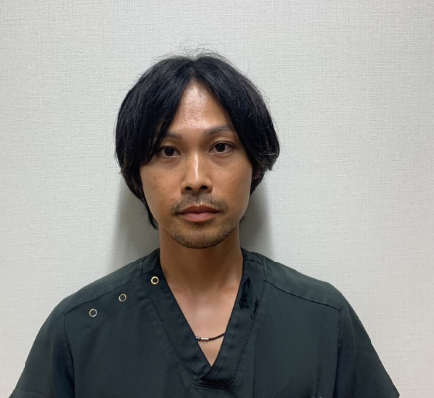
臨床ですぐに使える!高齢者のバランス評価と転倒予防アプローチ(14日間の見逃し配信付き)
2026年3月13日(金)オンライセミナー

運動器疾患に対するリハビリテーションの考え方の基礎 ─ 受傷機転・疼痛・動作分析からみる臨床の視点(14日間の見逃し配信付き)
2026年3月9日(月)オンライセミナー
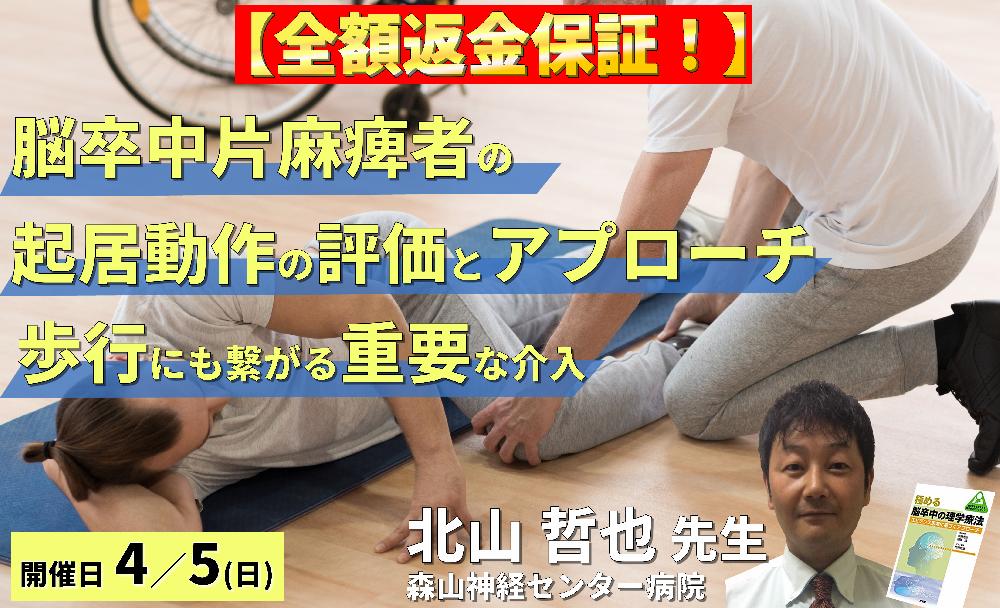
【全額返金保証付き】脳卒中片麻痺者の起居動作の評価と運動療法~座位・起立・歩行にも繋がる「極めて重要」な介入~ 講師:北山哲也先生
【全額返金保証】 内容にご納得いただけない場合は、料金を全額返金いたします。 ※購入より1週間以内が対象となります ※決済・返金手数料はご負担いただきます ーーーーーーー ◇こんな悩み...

【全額返金保証付き】PT・OT・STのための運動器画像読影とリハビリへの応用(上肢編)~運動機能評価という視点から軟部組織損傷を読み解く!~ 講師:瀧田勇二先生
【全額返金保証】 内容にご納得いただけない場合は、料金を全額返金いたします。 ※購入より1週間以内が対象となります ※決済・返金手数料はご負担いただきます ーーーーーーー ◇こんな悩み...

