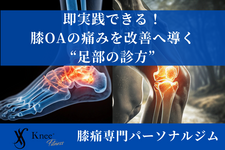27日、参議院予算委員会において、理学療法士でもある自由民主党全国比例区選出の田中まさし議員が、医療専門職の賃金問題や人材育成制度について質問を行いました。特に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の状況に焦点を当て、賃金の停滞や資格取得後の継続教育の必要性について石破総理や福岡厚生労働大臣に見解を求めました。
質問は多岐にわたったが、すべてに共通していたのは「支える人を支える社会を」という一貫した姿勢でした。
産後ケアに理学療法士の役割が明記された意義
今回の質疑のなかで注目すべき点、産後ケアにおいて理学療法士の役割が正式に位置づけられたことです。三原じゅん子少子化対策担当大臣は、令和5年10月に改訂された産後ケアガイドラインで、「腰痛や尿失禁などの産後症状」に対応する専門職として、理学療法士が新たに明記されたことを報告しました。これは、リハビリ専門職が新たな分野で活躍する道を開くとともに、社会課題の解決に貢献できる重要なステップといえるでしょう。
「また私たちは置いていかれるのですか」──進まないリハ職の賃上げ
田中議員が特に声高にしたのは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリ専門職の賃金水準の低さでした。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」のデータによると、これらの職種の賃金は2002年からほぼ横ばいで推移しており、昨今の物価上昇に対してまったく追いついていない状況です。
さらに、リハビリテーション専門職団体協議会の調査では、医療施設の3割、介護施設の4割で昇給すらされていないという厳しい実態が明らかになりました。
田中議員は、「また私たちは置いていかれるのですか」という現場からの声を紹介し、次のように訴えました。
「このような状況では、将来に希望を持って働くことが困難です」
これに対して福岡厚生労働大臣は、令和6年度の診療報酬改定や補正予算を通じた支援を紹介しつつ、「必要な対応を検討してまいります」と答弁しました。
資格を取って終わりではない──卒後教育とキャリア支援の必要性
次に田中議員が焦点を当てたのは、医療専門職の卒後教育体制です。建設業界で導入されている「キャリアアップシステム」を例に挙げながら、医療職にも同様の制度設計が必要であると指摘しました。
「社会や医療の変化に対応するには、資格取得後も継続的に学べる仕組みが必要です。それが地域課題の解決にもつながるのです」
この提言に対し、石破内閣総理大臣は「キャリアアップと賃金向上の連動は極めて重要」と述べ、来年度から「医療関係職種の卒後教育に関する調査研究」を開始する方針を示しました。制度化が進めば、療法士がスキルを高め続ける環境づくりと、それに見合う処遇の実現が期待されます。
地域リハの持続可能性──過疎地で進む“サービスの空白化”
また、地域におけるリハビリテーション体制の維持についても、田中議員は危機感をもって問題提起しました。独居高齢者の増加、施設の閉鎖、人材の流出により、在宅でのリハビリテーションが提供しにくい地域が増えており、なかには「医師が不足してリハビリの指示が出せない」という地域もあると指摘しました。
「一人の専門職が多様な支援ができるようになること、また地域に応じた規制緩和が必要です」
福岡厚労相は、令和6年度の介護報酬改定において、介護老人保健施設や介護医療院が訪問リハ事業所として機能できるよう制度を緩和したことを説明し、今後も地域の実情に応じた制度改善を進めると述べました。
まとめ──「支える人を支える」政治へ
田中まさし議員による質疑は、現場の声を真正面から国会に届け、療法士の未来を形づくるための重要な問いを政府に投げかけるものでした。リハ専門職のキャリア支援、賃金の是正、地域のリハ体制の再構築──。いずれも「人を支える人」を支える社会の基盤であり、これらをどう整えていくかは、まさに政治の使命です。今後、制度の具体化がどのように進んでいくのか。引き続き注視していく必要があります。
▶︎https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
全文掲載
*一部修正。
田中まさし議員: おはようございます。自由民主党全国比例区選出の田中まさしでございます。今日は鶴保委員長をはじめですね、理事関係の皆さま方には質問の時間をいただきまして、ありがとうございました。昨年の通常国会が終わりましてからですね、約半年ほどをかけまして、全国47の都道府県を訪問させていただきまして、現場の声を数多くいただきましたので、そのお声を元にして今日は質問させていただきたいというふうに思っております。
最初にですね、この出産後の女性の健康問題について、三原大臣に伺いたいと思います。女性がキャリアを中断しないこのことはですね、この男女間の賃金格差の是正、女性の経済的自立につながるということは言われているところであります。離職することなく、キャリアを形成していくためには、仕事・家事・育児の両立支援に加えまして、この女性特有の症状がございます。これにふまえたですね、健康への理解、支援等の健康との両立ということも私は必要だというふうに思っております。
女性の年齢階級別労働力を30代で低下するM字カーブこれは徐々に良くなってきているところでありまして出産に伴う離職、休職少なくなっていると思いますが、この健康問題へ理解、支援というのは今後もますます必要になってくるというふうに思っております。この日本女性財団の調査で出産後に生じる身体症状として腰痛が63.6%、尿漏れが53.2%肩の痛みは44.4%に方に発生しておってそのうち医療機関を受診したのはわずか15%という状況で職場復帰にも影響があったという回答があります。
この産前産後の女性の症状があった際にですね医療機関への受診につなげる仕組みこれが必要だというふうに思っております。この産後の身体変化による症状に悩む女性のサポートについて適切な医療へのアクセスそれから地域の専門家による支援こういったものをですね体制を整えていく必要があるというふうに思っておりますが大臣のご見解を伺いたいと思います。
三原担当大臣: はい。委員ご指摘の通り産後の心身の変化に悩む女性に対して健康はもとより職場復帰や子育て支援の観点からもですねしっかりとサポートしていくことは重要だと考えております。子ども家庭庁では産後間もない時期に身体的機能の回復状況や精神状態の把握などを行う産婦健康診査への費用助成、これを行っておりましてその結果に応じて医療機関や産後ケア事業などの適切な支援につなげていくことを推進をさせていただいております。
その上でですね昨年10月に産後ケア事業のガイドラインを改訂いたしまして対象となるケアに産後の腰痛ですとか尿失禁等も含まれることを明確化するとともにこうしたケアへの適切な支援を担っていただく観点から産後ケアの実施担当者として理学療法士も追加をさせていただいたところでございます。産後の変化に悩む女性それぞれのニーズに応じてですね様々な専門家による適切な支援が行われるよう引き続き取り組んでまいりたいと思っております。
田中まさし議員: ありがとうございます。男女共同参画白書なんか見ますとですねこの健康上の問題を抱えている女性どう対応してますか?という問いにですね何もしないという人が一番多い、次に多いのが市販薬、サプリで対応する、3つ目は休むと仕事を休むという状況、これ問題の解決になってないんですよね。そうするとやっぱり長期化していきますんでやっぱりその人の豊かな暮らし幸せな日常生活に大きく影響すると思いますので引き続きぜひ前に進めていただければというふうにおります。ありがとうございました。
次はですね医療介護福祉等従事者の賃上げについてで福岡大臣に伺いたいと思います。今年の連合の調査で第2回の集計会結果従業員300人未満の中小でもですね4.92%昨年上回っているという状況であります。医療介護分野はですね昨年の報酬改定で今年2%2.92%の開きがもうこの中小と比べても生じるという見込みであります。この状況を何とか解決しませんとですねこの業界からの人材流出ますます歯止めがかからない状況になっていくというふうに考えているところであります。
先日もある方々からまた私たちは置いてかれるんですか?とこういう切実な声私も現場から聞いており、令和6年度昨年の診療報酬改定でベースアップ評価料ですね現場の皆さん方の賃金を挙げていく仕組みを導入していただきました。大変ありがたかったなというふうに思っておりますが対象外の職員もいる事務職員とか、こうなりますとやっぱり経営者の皆さん方やっぱりやめられたら困りますから防衛的な賃上げをしなきゃいけない持ち出しであります。この声も経営者の皆さん方から本当に多く聞きました。これはみんなで仕事してるわけですから、みんなにも手当てをしなきゃいけない、それで一つの経営が成り立っているというわけでありますんでここもですねしっかりと対応していかなきゃいけないというふうに思っております。
またですね私の母体である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の団体は賃上げ自体がされてないという方が相当数います。資料1をご覧ください。これは賃金構造基本統計調査の状態です。右側の方見ていただくとこの緑の線ですがこの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士2002年と比べて変わってないです横ばい。こんなに物価が上がってるのに。こういった状況です。
それから次ですね資料の2もご覧いただければというふうに思っております。これはリハビリテーションの専門職団体協議会が全施設を対象に調査した結果であります。赤字のところですね医療施設では3割、介護福祉施設で4割の施設で昇給すらされてない。ベースアップどころの騒ぎじゃないんですね。賃金すら上がってないという状況であります。


こういった状況のですね実態を受けてこのまあ2.92%のこの賃上げこれどう是正していくのか、またですねこの賃金が上がってない方も多数いらっしゃるというくまなく賃金を上げていくということについてどう取り組んでいかれるのか、政府は物価を上回る賃上げとかねてから打ち出されていますのでこの部分についての政府の対応ですね福岡大臣から力強くいただければと思います。
福岡厚生労働大臣: まず委員に置かれてはこれまで一貫してですねリハ職をはじめとする医療関係、介護関係の職種の方々の処遇改善であったり勤務環境の改善に向けて様々ご尽力いただいていることを心から敬意を表させていただきたいと思います。
ご指摘いただきありましたようにそのリハ職はじめですね様々なその関係職種の方々の賃金が他の産業より低い現状を鑑みれば賃上げの実現は大変重要な課題だというふうに認識をしております。政府といたしましては先ほどご紹介ありましたその令和6年度報酬改定の対応に加えまして先の補正予算でさらなる賃上げに向けた支援を講じてきているところでございまして、その昨年の補正予算、これがまさにこれから現場に行き届くような時期になってまいります。あの物価等の動向、経営状況など足元の情勢変化や現場からのご意見もしっかり把握した上で、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
田中まさし議員: よろしくお願いいたします。業界の中で調査した結果もですねほとんどこういう状況になってますし、5年前に比べて賃金が上がっているか下がってるか変わらないかという調査をしたところですね、上がってない下がっているというものが34.2%もいるっていう5年前と比較してですねこういう状態でですね将来に希望を持って仕事するということ自体がこれ困難な話であります。
その上でですね、先ほどの防衛的賃上げのお話もしました医療介護施設自体の経営が非常に厳しい状況の中でこの予算フレーム、これに関しては物価高騰と賃上げ分が入ってないですね。これはこの予算フレーム自体をもうしっかり見直していかないとこれデフレ下のフレームですんで、これはですね次の骨太の方針の時にですねしっかりこれも検討していただきたいなというふうに考えているところであります。
それから次ですね、医療専門職の資格取得の育成について総理にお伺いしたいと思います。医療専門職の育成に関してはこの資格取得後も継続して行っていかなければならないというふうに思っております。サービスの高付加価値化、生産性の向上これも政府を挙げて取り組んでいらっしゃいますが機械やシステムの高付加価値化も大事なんですが、人の幸福価値化が極めて医療現場についてはこの技術職については非常に大事であります。
この医療技術、治療法はもう毎日日々進歩しておりまして、資格取得時のですね知識や技能だけでは常に最善の医療を提供し続けることは極めて困難であります。最新知識を学んで技能を磨き続けられる環境、これをですね提供し続けることということが大事でありますし、そのことが地域課題の解決にしっかりつながっていくということを進めていく必要があろうかと思います。
現状ではですねこの資格取得の研修や継続教育の支援がちょっと十分と私は言えないではないかなと思ってます。医療の質を高めて、患者により良い医療を提供するためには建設業におけるキャリアアップシステムのようなですね資格取得後の人材育成を明確に位置づけて賃上げに結びつくような体系的な支援を国の制度の中に構築するべきだというふうに考えております。
21日我が党の清水正人議員の同様の質問について石破総理からはですね、このいかにこのキャリアアップが賃金向上につなげていくかが重要という答弁をされていらっしゃる。まさにおっしゃる通りだというふうに私も思うところであります。この医療専門職の人材育成の在り方、地域課題にしっかり対応していく人材育成を政府として国としてしっかりと育成していくんだとこの取り組みについてですねご意見をご見解を伺いたいと思います。
福岡厚生労働大臣: 医療専門職種の養成につきましては厚生労働省において求められる知識技能の変化、臨床や教育の現場の状況等を踏まえながら養成のカリキュラムの見直しを行うなど質の高い医療専門職の養成に努めているところでございます。
ご指摘の資格取得後の人材育成についてはプロフェッショナルオート・ノミーの考え方に基づき自己研鑽であったりOJTに加え各医療専門職の職能団体が行う研修などを通じまして必要な知識技能を身に付けていただいているものと承知をしておりますが制度的な対応の一例といたしまして診療報酬においても専門性の高い一部の診療項目における施設基準において医療関係団体等が主催する研修の受講を要件としている例もございます。
厚生労働省としては医療専門職による安全で質の高い医療を提供いただくことは大変重要だというふうに考えておりまして専門職の方々が専門性を高め、その力を発揮いただくためにどのようなことができるか来年度から医療関係職種の方々の卒後教育に関しまして調査研究を行うこととしておりまして、その結果も受けまして、卒後教育のあり方についてしっかり整理して参りたいと思います。
石破内閣総理大臣: 現場を一番ご存知の一人であられます田中委員のご見解は感銘深く拝聴致したところであります。今の建設業におけるキャリアアップシステムについての言及を頂戴をいたしました。私も長く建築板金、あるいは左官業そういうような議連のお世話をさせていただいているところでございますが、建設業、建築業においてキャリアアップシステムというものを導入してそれ自身が国家資格でない場合が多いんですが、しかし一生懸命努力をして技能を高めていった人がそれにふさわしい処遇が受けられるということをきちんと確立をしなければいかんということでやってるところでございます。
今厚生労働大臣からお答えしましたように医療現場のおきまして、多くの資格を持たれる専門職の方々にご活躍をいただいているわけで特定の専門職の方のキャリアパスを一律に論ずるっていうのは難しいんですが各職種が知識技能を高めて、それがより良い処遇のもとでより良い医療チームとして提供するということは極めて重要であります。そしてキャリアアップを感じられるようにするということそれによって賃金が上がっていくということが極めて重要でありまして、就職されました後の知識技能の習得は自己研鑽、OJTに始まり職能団体による研修を通じて行われているわけでございます。
対応の一例として一定の研修を受けられた理学療法士の皆様方のリハビリテーションを診療報酬上要件としている例もございます。その上で着実な賃上げがとにかく重要でございますから、まずは補正予算による支援が現場に届くように取り組み、さらにその状況を踏まえた必要な対応が重要であります。で専門職の方々が専門性を高めてその力を遺憾なく発揮していただく、そのためにどのようなことができるかということでございまして、大臣からお答え申し上げましたように、来年度から医療関係職種の方々の卒業教育に関し、調査研究を行うということといたしております。
その結果も受けまして卒後教育の在り方について整理をいたしてまいりますが、いずれにいたしましても、キャリアをアップされた方々がそれにふさわしい報酬というものを受けられるように政府として着実に確実に努力をいたしてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。
田中まさし議員: 総理ありがとうございました。本当にあの今総理おっしゃったことを業界の皆さん方大変お力強いお言葉だったなというふうに思っております。大臣からもお話がありました卒業研修のあり方これとても大事でありまして社会構造、社会実情が大きく変わっていく中で、資格取得時の状況と今例えば理学・作業療法士法なんては60年前に制定された法律で60年前の概念が今で頑張れということになってもですねこれは研修全く追いつかない状況になってきます。
これからの社会が変わっていく中に適合した研修を卒業後にしっかりと研修していけませんと資格があっても地域課題解決できないのではこれは国としての私は損失だというふうに思っておりますのでぜひですねそこはお願いをしたいというふうに思っております。
次に参ります。次はですね地域のリハビリテーションサービスの提供体制についてお伺いしたいと思います。全国訪問して思うことは独居高齢者の方がもう極めて増えていると思います。それから医療介護施設の経営側も大変厳しい状況。もういつ何時というお声も数多く聞きます。それから人材の流出が非常に加速しているということであります。
この地域の多様な人材がもう連携しながら支えていくってことも大事ですけども一人の人間が多様な支援ができるという能力を磨いていくことも同時に私は必要だというふうに考えています。実際地域の現場ではですねこの医療介護施設がどんどん縮小していく状況の中で、在宅のリハビリテーションが提供しづらいという声もあります。それから医師の偏在等もありましてですねリハビリテーションの指示が実際「出なくなりました」と言われる地域も正直あります。それから看護師がやっぱりこれも現場で不足するために、訪問看護ステーション2.5人集めるのにも苦労している事業所がいっぱいあって縮小しなきゃいけないという状況の地域がいっぱいあります。
なのでこれは全国というかそういう地域の実情に応じたですねあの規制緩和っていうのは私はしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。とりわけこの過疎地人材が少なくなっている過疎地においてですねこの職種ごとに決められた役割や人員基準が、地域住民のサービス享受を阻害していないのかどうかというこの現行の基準の問題の検討、それから地域のリハビリテーションニーズや人材の状況、提供状況を踏まえた上で地域の実情に応じて訪問看護ステーションの人員配置要件の緩和であったりあるいは医療機関との連携を踏まえた訪問リハビリテーション事業所の創設などを実際的にきちっと在宅でのリハビリテーションを提供できる体制、これを維持していく必要があるんではないかなというふうに考えておりますが、厚生労働大臣の見解を伺いたいと思います。
福岡厚生労働大臣: 委員ご指摘のように全国どこでもですねあの必要なサービスを受けられるためには限られた医療人材またその介護人材をですね有効に活かしていくということは極めてな視点だというふうに思います。
ご指摘の訪問看護ステーションであったり、訪問リハビリテーションの人員配置基準につきましては質の確保されたサービスを安定的に提供するために定められているものでございますが、一方であの在宅での療養が必要なご高齢者の生活を支えるために訪問看護であったり、訪問リハビリテーションなどのサービスが中山間地も含め安定的に提供されることは重要でございまして、令和6年度の介護報酬改定ではサービス提供の拡大を図りますため、例えば介護老人保健施設や介護医療院については訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなし事業所指定の手続きを行わなくても、サービス提供を可能とするようにしたところでございます。
あの2040年に向けましては、人口減少によるサービス需要の変化に地域差がありますことから介護サービス提供体制や人材確保の在り方などについて本年の1月から有識者等で構成される検討会を設け今議論を行っていただいている最中でございます。こうした議論も社会保障審議会介護保険部会の制度改正などの議論に生かしてまいりたいと思います。
田中まさし議員: ありがとうございました。終わります。