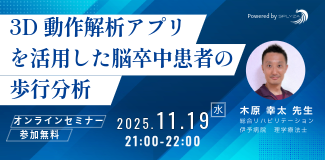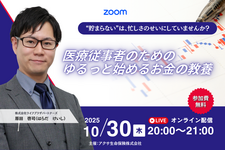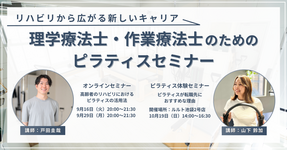目次
- はじめに
- 1. 国民医療費が示す「需要規模」
- 2. NDBが示す「供給実態」
- 3. 単位数を金額に換算する試み
- 4. 疾患群別にみる「需要」と「供給」
- 5. 既存研究との比較
- 6. 地域移行の兆し
- まとめ
- 参考文献
はじめに
2025年10月10日、厚生労働省は「令和5(2023)年度 国民医療費の概況」を公表した【1】。国民医療費はわが国の医療経済の根幹を示す統計であり、令和5年度の総額は48兆915億円に達した。しかし、リハビリテーション費用は独立項目としては示されず、医科診療医療費(34兆5,498億円)の中に埋没している。
この「見えないリハ費」を可視化するため、本稿では国民医療費の疾患別費用構造【1】と、第10回NDBオープンデータ【2】を重ね合わせ、需要と供給の両面からリハビリテーション市場規模の実像を描き出す。
1. 国民医療費が示す「需要規模」
リハビリと深く関わる疾患群の国民医療費は以下の通りである【1】。
- 循環器系の疾患:6兆2,834億円(18.2%)
- 筋骨格系疾患:2兆7,581億円(8.0%)
- 損傷・中毒・外因:2兆6,977億円(7.8%)
- 神経系疾患:2兆3,053億円(6.7%)
合計で約13兆円超(医科診療医療費に占める割合で約41%=総額基準で約29%)がリハ対象疾患群であり、巨大な「潜在市場規模」を構成する。
2. NDBが示す「供給実態」
第10回NDBオープンデータ(2023年度算定分)【2】による主要リハの算定単位数は以下の通りである。
- 脳血管疾患等リハ:1.73億単位
- 運動器リハ:2.26億単位
- 廃用症候群リハ:0.50億単位
- 呼吸器リハ:0.19億単位
- 心大血管リハ:0.11億単位
- がんリハ:0.06億単位
合計で約4.85億単位 が提供されており、需要に応える「供給量」を示している。
*なお、NDBには性年齢別・都道府県別の集計値も存在するが、部分集計のため全国合計は小さく算出される。本稿では全国値を持つ診療月別を基準とした。
⇆ 横にスワイプして各分類の全国合計(単位数)を比較できます
脳血管疾患等リハ 全国合計
(単位:回/単位数)
診療月別(基準):172,766,735
性年齢別:2,463,005
都道府県別:15,227,159
注:診療月別がフル集計の基準値。ほかは部分集計。
運動器リハ 全国合計
(単位:回/単位数)
診療月別(基準):226,257,243
性年齢別:3,402,484
都道府県別:19,971,528
注:診療月別がフル集計の基準値。ほかは部分集計。
廃用症候群リハ 全国合計
(単位:回/単位数)
診療月別(基準):49,985,885
性年齢別:876,160
都道府県別:4,215,454
注:診療月別がフル集計の基準値。ほかは部分集計。
呼吸器リハ 全国合計
(単位:回/単位数)
診療月別(基準):18,645,760
性年齢別:377,833
都道府県別:1,609,854
注:診療月別がフル集計の基準値。ほかは部分集計。
心大血管リハ 全国合計
(単位:回/単位数)
診療月別(基準):11,190,635
性年齢別:154,428
都道府県別:1,037,618
注:診療月別がフル集計の基準値。ほかは部分集計。
がんリハ 全国合計
(単位:回/単位数)
診療月別(基準):6,451,020
性年齢別:74,436
都道府県別:538,459
注:診療月別がフル集計の基準値。ほかは部分集計。
合計(6分類) 全国合計
(単位:回/単位数)
診療月別(基準):485,297,278
性年齢別:7,348,346
都道府県別:42,600,072
注:診療月別はフル集計値。性年齢・都道府県は部分集計の全国相当。
3. 単位数を金額に換算する試み
代表点数(脳血管200点、運動器180点、廃用170点、呼吸190点、心大血管200点、がん160点)を仮置きし、感度分析(−10%〜+15%)を行った結果を「表1」に示す。年間総額は約0.906兆円(ベース)で、国民医療費に占める割合は総額比約1.9%(医科診療比でも約2.6%)である。
⇆ 横にスワイプして分類ごとの換算レンジを比較できます
脳血管等代表点数 200点
低位 3,109.8 億円
ベース 3,455.3 億円
高位 3,973.6 億円
単位数:172,766,735
運動器代表点数 180点
低位 3,665.3 億円
ベース 4,072.6 億円
高位 4,683.5 億円
単位数:226,257,243
呼吸器代表点数 190点
低位 318.8 億円
ベース 354.3 億円
高位 407.4 億円
単位数:18,645,760
心大血管代表点数 200点
低位 201.4 億円
ベース 223.8 億円
高位 257.4 億円
単位数:11,190,635
がん患者代表点数 160点
低位 92.9 億円
ベース 103.2 億円
高位 118.7 億円
単位数:6,451,020
廃用症候群代表点数 170点
低位 764.8 億円
ベース 849.8 億円
高位 977.2 億円
単位数:49,985,885
合計概算レンジ
低位 8,153.1 億円
ベース 9,059.0 億円
高位 10,417.8 億円
注:代表点数は仮置き/加算・計画書料等は未反映のため推計。
4. 疾患群別にみる「需要」と「供給」
「表2」は、疾患群ごとの需要(国民医療費)と、対応領域の供給(NDB単位数合算)を並べたものである。金額と単位は異なる指標である点にご留意いただきたい。
⇆ 横にスワイプして疾患群ごとの需要(億円)と供給(万単位)を比較できます
循環器系疾患需要
6兆2,834億円
供給:脳血管・心大血管リハ合算(診療月別)
供給(NDB 単位)
18,396 万単位
注:183,957,370 単位
筋骨格系疾患需要
2兆7,581億円
供給:運動器リハ(診療月別)
供給(NDB 単位)
22,626 万単位
注:226,257,243 単位
損傷・中毒・外因需要
2兆6,977億円
供給:運動器+廃用リハ(診療月別)
供給(NDB 単位)
27,624 万単位
注:276,243,128 単位
神経系疾患需要
2兆3,053億円
供給:脳血管・廃用・呼吸器・がん(診療月別)
供給(NDB 単位)
24,785 万単位
注:247,849,400 単位
読み解きのポイント
- 循環器系(6.2兆円):対応するリハは脳血管・心大血管で 1億8,396万単位。費用の大きさに比べると、提供単位数は比較的コンパクト。
- 筋骨格系(2.8兆円):運動器リハで 2億2,626万単位。費用規模に比して単位数が大きく、外来比率の高さが特徴。
- 損傷・外因(2.7兆円):運動器+廃用で 2億7,626万単位。事故や外傷後リハが幅広く供給されている。
- 神経系(2.3兆円):脳血管・廃用・呼吸器・がんで 2億4,787万単位。高齢者中心で幅広い疾患に対応。
▶︎ 13兆円規模の需要(国民医療費)に対し、供給側は年間約4.85億単位、金額換算で約0.9兆円規模と推計される。両者の比率が適正かどうかは一概には言えないが、この差はリハ費が医療費全体の中で占める「見えにくさ」を示している。
5. 既存研究との比較
既存研究もNDBを用いた「単位数ベース」の分析を行っている。
- 厚労科研報告(佐藤ら, 2023)【3】は2018〜2022年の提供量推移を示す。
- 学術論文(山本ら, 2023)【4】は脳血管リハが入院リハの46%以上であること、80歳代前半が最多であることを報告している。
- 市場調査(富士経済, 2022)【6】は機器市場の金額規模を示すが、診療報酬ベースとは指標が異なる。
これらの知見と照らすと、本稿の試算(約0.9兆円)は、提供量の規模感・分野別構成比とも整合的であり、加えて「金額ベースの見積もり」という新規性を持つ。
6. 地域移行の兆し
国民医療費に含まれる周辺項目も重要である【1】。訪問看護医療費は5,727億円(+23.6%)、あん摩・マッサージ・はり・きゅうは757億円(+12.6%)、柔道整復師は3,213億円(−1.1%)。これらは、リハが病院から地域・在宅へ拡大していることを裏付ける。
まとめ
- 需要(国民医療費):13兆円超
- 供給(NDB換算):約0.9兆円(国民医療費総額比 約1.9%、医科診療比 約2.6%)
- 整合性:既存研究(提供量推移・構成比)と概ね一致
- 新規性:NDB単位数に基づく金額換算による「見えないリハ費」の可視化
「二大データ」を重ね合わせることで、リハ専門職が直面する市場の全貌と、将来戦略に向けた方向性が明らかになる。
医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアの創業を経て、これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。
近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。
参考文献
- 【1】厚生労働省. 令和5(2023)年度 国民医療費の概況. 2025年10月10日公表.
- 【2】厚生労働省. 第10回NDBオープンデータ. 2023年度算定分.
- 【3】佐藤太一ほか. リハビリテーション提供量の推移・需要推計に関する研究. 厚生労働科学研究費補助金 報告書, 2023.
- 【4】山本一郎ほか. 「日本における入院リハビリテーションの実施動向」, Journal of Clinical Rehabilitation, 2023.
- 【5】WHO. Rehabilitation services and related health databases, Japan. 2022.
- 【6】富士経済. リハビリ関連機器・システム市場に関する調査, 2022.