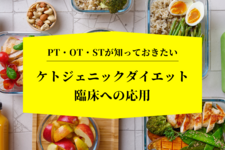目次
- はじめに
- PT向け:筋量維持と運動機能回復の最適化
- OT向け:認知機能と日常生活動作の統合的支援
- ST向け:嚥下機能と栄養安全性の管理
- 共通課題:多職種連携と安全性管理
- 実践への提言
- 今後の展望
- 参考・引用文献
はじめに
ケトジェニックダイエット(KD)は、1920年代に難治性てんかんの治療法として開発された高脂肪・低炭水化物の食事療法です。近年、その適応範囲は大きく拡大し、神経疾患、代謝性疾患、さらにはリハビリテーション領域まで臨床応用が模索されています。
2025年に発表されたPaoliらの総説では、ケトジェニックダイエットが単なる「減量法」ではなく、神経保護・代謝調整・炎症制御を担う"栄養代謝療法"として位置づけられることが示されました[1]。特に重要なのは、従来の「ケトトキシック(ケトン体有害)」という概念から「ケトホルメティック(適度なストレスによる有益効果)」へのパラダイムシフトです[1]。
本記事では、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)それぞれの専門性に即して、ケトジェニックダイエットを"自分ごと化"できる臨床応用について解説します。
PT向け:筋量維持と運動機能回復の最適化
肥満・2型糖尿病患者における体組成改善
理学療法士が関わる肥満や2型糖尿病患者において、ケトジェニックダイエットは体重減少とインスリン抵抗性改善に有効であることが複数のランダム化比較試験(RCT)やメタ解析で確認されています[2]。
特に注目すべきは、Klonekらが2024年に報告した12週間の介入研究です[3]。肥満女性を対象とした研究では、ケトジェニックダイエットにより体脂肪減少と血糖・脂質代謝の改善が認められました。理学療法士にとって重要なのは、減量に伴う筋量減少がリハビリテーション効果を妨げる懸念です。しかし、2025年のAthinarayananとVolekのレビューでは、ケトジェニックダイエット下でも適切な運動療法との併用により筋力維持が可能であることが示唆されています[4]。
臨床実践のポイント:
- 導入初期2-3週間は「ケトフル」による一時的な運動能力低下に注意
- 低~中強度の有酸素運動から開始し、段階的に負荷を調整
- ケトン体適応完了後(3-4週間後)は持久的運動能力の向上が期待可能
神経疾患での運動機能回復