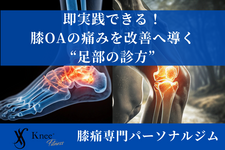中重度者対象ホームに登録制導入へ ― 透明性確保と囲い込み防止を柱に
厚生労働省は10月31日、「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」(第7回)を開催し、約半年間にわたる議論の取りまとめ案を大筋で了承しました。本案では、中重度の要介護者や医療的ケアを要する高齢者を受け入れる有料老人ホームに対して登録制(事前規制)の導入を求める方向性が明確に打ち出されました。また、入居契約の透明性や入居者紹介事業の公正性確保、いわゆる「囲い込み」対策など、多岐にわたる制度改善の方向が示されました。
パブリックコメント157件 登録制導入に賛成意見多数
冒頭で厚生労働省老健局高齢者支援課の落合課長が、10月8日から21日まで実施されたパブリックコメントの結果を報告しました。個人・団体計57者から157件の意見が寄せられ、「運営・サービス提供」(74件)、「指導監督」(30件)、「囲い込み対策」(52件)の3分類で整理されたと説明しました。
寄せられた意見の多くは、登録制導入による安全性・質の確保を支持する内容であり、職員配置の充実や中小事業者への配慮を求める声も上がりました。入居者紹介事業の透明性確保については、現行の届出・公表制度を基盤に、公益法人等が「優良事業者」として認定する仕組みを設ける方針に賛同する意見が見られました。一方で、「制度が排除的なものとならないよう留意すべき」との懸念も示されました。
登録制の対象をめぐり議論 「全ホーム対象」か「中重度限定」か
今回の会合では、登録制の対象範囲をめぐり活発な意見交換が行われました。
日本医師会の江澤和彦常任理事は、「高齢者はいつ脳卒中や心筋梗塞、転倒による骨折などを起こすか分からない。要介護3以上になったら退去というのは入居者の尊厳に反する」と述べ、「すべての有料老人ホームを登録制の対象にすべきだ」と主張しました。
これに対し、日本介護福祉士会の矢田立郎副会長は、「まずは安全確保の緊急性が高い中重度の要介護者を受け入れるホームを対象にすべきだ」と発言し、段階的導入の必要性を訴えました。
さらに、全国有料老人ホーム協会の松尾参考人(上村構成員代理)は「これまでの議論を丁寧に整理した内容で、おおむね合意できる」としつつも、
「特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設は登録制の対象から除外することも含め、より現場実態に即した運用を検討すべき」と述べました。
情報公表システムの改善と透明性向上を要望
**大阪府の木本和伸構成員(府福祉部高齢介護室課長)**は、介護サービス情報公表システムの現状について、「都道府県が登録を代行しており、事業者が直接入力できない仕様になっている」と指摘しました。
その上で、「システム改修にあたっては利用者の利便性だけでなく、自治体の事務負担にも十分配慮してほしい」と述べました。
「囲い込み」対策 ケアマネ契約の独立性を明文化
取りまとめ案では、入居契約とケアマネジメント契約を独立したものとして明確化することが盛り込まれました。
契約締結プロセスに関する手順書やガイドラインを整備し、入居希望者に提示することで透明性を確保する方針です。また、住まい事業と介護サービス事業の会計を分離・独立して公表し、収支構造を可視化することも求められました。
東洋大学の高野龍昭教授は、「中重度者を受け入れるホームには一定の事前規制が必要だが、軽度者の場合は自己決定・契約能力が高い。介護・医療制度側で支援を検討すべき」と述べ、
規制対象を区分する方向性を示しました。
特定施設への移行促進も課題に
さらに、住宅型有料老人ホームから特定施設入居者生活介護への移行促進を明記。
「入居者が必要とする介護サービスが特定施設と同等の場合には、特定施設への移行を促す仕組みが必要」との方向性が示されました。
今後の展開 介護保険部会で制度化へ
座長の駒村康平・慶應義塾大学教授は、「4月以降、有料老人ホームの運営やサービスのあり方をめぐり多面的な論点を議論し、本日ようやく取りまとめに至った」と述べました。
閉会にあたって、厚生労働省老健局の黒田秀郎局長は次のように総括しました。
「有料老人ホームは、高齢者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら自立した暮らしを継続し、その人らしい人生を全うできる安心・安全な住まいとして期待されています。
今後は社会保障審議会介護保険部会で報告し、制度改正に向けた検討を進めてまいります」
本検討会の取りまとめは、近く厚労省ウェブサイトで公表されたのち、介護保険制度の次期改正論議の重要な基礎資料となる見通しです。