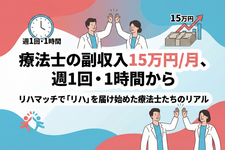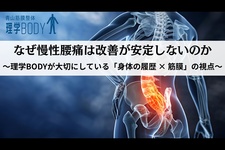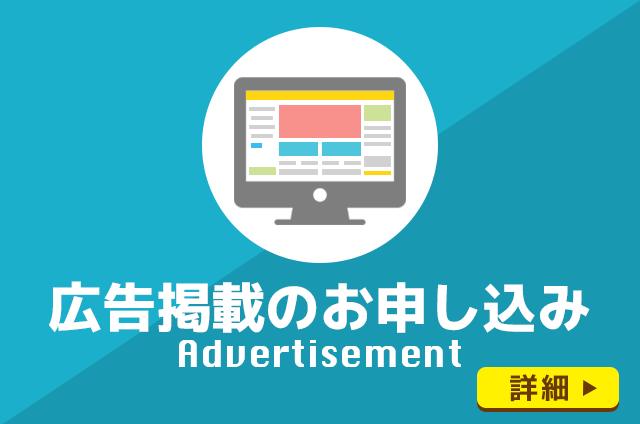Voice ─ 現場からの提言
病院を飛び出したい若手理学療法士が、
荒野で生き残るための「生存戦略」
Vol.2 ─ 「個」の信頼と「組織」の力。2040年への道標
話が「制度」から「人」に移った瞬間、鶯春夫氏の纏う空気が少し変わったように見えた。窓の外では、依然として冬の風が唸りを上げている。 ガタガタ、と窓が鳴く。 その乾いた音は、これから荒野へ向かう若手への、冷徹な警告のようだった。
2025年。病院のポストは埋まり、先が見えない。閉塞感に覆われた若手たちの目は、副業や他職種への転職といった「外」の世界に向き、静かな人材流出が続いている。
「このままで、一生を終えるのか」
焦燥感に駆られ、地図を持たずに荒野へ飛び出そうとする彼らに、鶯氏は「答えは足元にある」と説く。
現在、徳島文理大学教授、(公社)徳島県理学療法士会会長という公的な重職を務める鶯氏。 1997年に「うぐいすリハビリ研究所」を立ち上げ、2010年に大学教授に就任するまで、組織に属しながらフリーランスとしても活動するという、当時としては異例のスタイルを貫いてきた。
その足跡を辿ると、彼が築き上げた「独自の地位」は、決して逃避や巧妙な計算から生まれたものではなく、「臨床への没頭」という極めて泥臭いプロセスの副産物であることが見えてくる。
「個」の信頼はいかにして作られるか
最近、SNSなどでは「フリーランス」という言葉が飛び交う。華やかな発信、自由な働き方。その響きに憧れる若手も多いが、鶯氏の道のりは、最初から独立を目指したものではなかった。鶯氏が選んだのは、臨床の現場で、患者と向き合い黙々とデータを積み上げる日々だった。
── 先生が「うぐいすリハビリ研究所」を立ち上げたのは、組織に縛られず自由にやりたいという動機だったのでしょうか?
鶯氏: いえ、最初は独立なんて考えてもいませんでした。 きっかけは、目の前の症例にとにかく向き合い、地道に学会発表を続けていたことです。3年目から四国理学療法士学会で発表し、5年目にはパネリストに選ばれました。 そうやってアウトプットを続けていると、「あの先生は詳しいらしい」と評判になり、少しずつ講演や指導の依頼が来るようになったんです。
── 営業活動をしたわけではなく、研究の結果として依頼が来た、と。
鶯氏: そうです。さらに大きかったのが、地元のテレビ番組への出演です。「おはようとくしま」という番組のリハビリコーナーを週1回担当することになり、そこから様々な方面から声をかけていただく機会が急増しました。 講演などの依頼が増えすぎて、個人の「副業」の枠では処理しきれなくなった。それで、当時の院長に相談して、勤務日数を週3日に減らしてもらい、残りの時間を研究所の活動に充てたのが始まりです。 つまり、「フリーになりたい」から作ったのではなく、仕事が殺到して「受け皿を作らざるを得なかった」というのが真実です。
── 当時ではかなり珍しかったフリーランスのような動き方をされていますが、若手にアドバイスはありますか。
鶯氏: 形態はどうあれ、「バイト感覚」で地域に来ることだけは避けてほしいですね。 地域の方々、特に高齢者は、相手が本気かどうかを敏感に見抜きます。「小銭稼ぎに来たのか」「本当に自分たちの生活を良くしようとしているのか」。薄っぺらな動機は、すぐに見透かされます。 まずは臨床で結果を出し、それを形(論文・発表)にする。その積み重ねがないまま外に出ても、地域からの信頼を得るのは難しいと思います。
「地図」としての組織論
個人の信頼が貯まるまでは、組織の力を借りればいい。鶯氏は「県士会(協会)」を、若手が地域に出るための「地図」であり「パスポート」だと定義する。多くの若手が協会から距離を置く中、彼は2014年の会長就任以来、組織という「器」を磨き上げてきた。それは、後進たちが安全に荒野を歩けるようにするための、彼なりの舗装工事だったのかもしれない。
鶯氏: 私が会長になった2014年頃から、組織のあり方を大きく変えました。「公益社団法人」を取得したことが最大の転換点です。これにより、県や市町村、警察といった公的機関との信頼関係が劇的に変わりました。
個人の理学療法士が警察に行って「協力させてくれ」と言っても門前払いですが、公益社団法人として行けば、対等に話ができるんです。
実際に徳島県士会は、県警と協定を結んでいる。障害者が自動車運転を再開できるかどうかの判定に、理学療法士が関わるのだ。入院患者を連れ、県警の運転免許センターへ行き、実車評価を行う。これは病院の中だけでは決してできない、新たな職域だ。
「誰でも派遣するわけではない」
現在、徳島県士会では、県や市町村から受託した事業に会員を派遣するシステムを構築している。報酬は時給換算で1万円程度になることもあるが、鶯氏は「誰でも行けるわけではない」と強調する。その口調には、会長としての厳しさが滲んだ。
鶯氏: 「地域に出たい」という意欲は買いますが、準備不足のまま派遣するわけにはいきません。我々のシステムでは、「介護予防推進リーダー」や「地域包括ケア推進リーダー」といった協会の指定する資格を取得し、所定の研修を受けた会員だけを講師として派遣します。
── 質の担保を徹底しているのですね。
鶯氏: 当然です。1回行けば報酬は出ますが、そこで評判が悪ければ「次はもう来なくていい」と言われます。行政との契約はシビアな真剣勝負です。だからこそ、病院に所属している間に研修を受け、リーダー資格を取り、協会の看板を背負って地域に出る。そこで実績を積み、顔を売る。信頼という貯金がたまった時、初めて「個人」への依頼が舞い込むようになるんです。いきなり丸腰で戦うのではなく、用意された「地図」と「武器」を持って地域に出てほしいと思います。
専門職が「いなくなる」ためのシステム
取材の終わり、鶯氏はふと視線を外し、窓の外、さらに先の未来を見据えていた。2040年。高齢者人口がピークを迎えるその時、もはや公的な医療・介護サービス(公助)だけでは社会は回らない。
鶯氏: これからは「互助」です。ただ、仲良く集まればいいという話ではありません。通いの場のリーダーが高齢化し、来られなくなったらその会は消滅してしまう。それでは意味がないんです。我々の仕事は、体操を教えることではありません。住民の中から次のリーダーを見つけ、育て、専門職がいなくても「住民だけで回るシステム」を構築することです。
── プレイヤーではなく、地域のプロデューサーになれ、と。
鶯氏: そうです。公助には限界があります。だからこそ、元気な高齢者が虚弱な高齢者を支える仕組みを作らなければならない。地域全体をマネジメントし、最終的には我々が「お役御免」になるような自立した地域を作る。それこそが、2040年を生きる理学療法士の新たな職能になるはずです。
「道は作りました。
あとは、やる気のある先生方が
来てくれるのを待つだけです」
◇
【編集後記】 ロサンゼルスへ繋がった「恩師の教え」
インタビューを終え、私はその足で、ある講演会へと向かった。登壇していたのは、ロサンゼルス・ドジャースで理学療法士として活躍する伊藤憲生(いとう・けんせい)氏だ。
華やかなメジャーリーグの舞台で働く彼が、学生たちに向けて語った言葉に、私は耳を疑った。
「目の前のことを突き詰めること。論文を書き、発表し、信頼を積み重ねること。それが次のキャリアにつながる」
それは数時間前、鶯氏が語った言葉と、驚くほど重なっていた。伊藤氏は徳島文理大学時代の鶯氏の教え子にあたるという。かつて将来に迷っていた学生時代の伊藤氏に、鶯氏はこう説いた。「とにかく行動して、形に残しなさい」
その教えを胸に、伊藤氏は卒業後、厳しい環境で臨床に打ち込み、論文を書き続けた。その泥臭い実績(アウトプット)が評価され、千葉ロッテマリーンズへの切符を掴み、そして現在は佐々木朗希投手と共にドジャースで戦っている。
「やり方は、ここにある」鶯氏はそう言った。
地域包括ケアシステムという足元の課題であれ、メジャーリーグという世界への挑戦であれ、道を切り拓く鍵は変わらない。近道はない。しかし、地図はある。30万円のデータを生み出したのも、メジャーリーガーを支える技術を生み出したのも、元を正せば「目の前の事象への問い」から始まっているのだから。
(了)
取材・文:今井俊太(POST編集部)